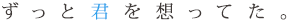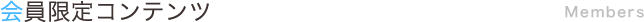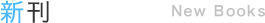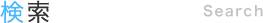うちの殺し屋さんが可愛すぎる
「聡一郎! あれが欲しい!」
そう言って亜鳥が袖を引っ張ったのは、初詣に訪れた神社の露店だった。聡一郎は品物が並べられた台の上を、眉を寄せて眺める。そこには亜鳥の年頃の青年が欲しがるようなものは、なにも乗っていなかったからだ。だが亜鳥の指先は、はっきりとひとつの商品を示している。
「お前まさか。これを結婚指輪にしたいとか思ってるんじゃねえだろうな」
それは空豆ほどの大きさの、アクリル製の青い宝石を模した飾りがついた、キラキラと光る指輪のオモチャだった。
「だって、絵本で見たのとすごく似てるよ」
「かもしれねえが、これは子供のオモチャだぞ。すぐ壊れちまうし、安物もいいとこだ」
「安いなら、高いよりいいじゃない」
それはそうかもしれないが、七百円は安すぎる。聡一郎としては、近いうちにきちんとした店でペアで名前を入れた、プラチナの指輪を用意しようと思っていたのだ。
亜鳥は紙で作られた箱から、指輪を手に取ってしげしげと眺めた。子供用のオモチャだから小さいが、ニッケルか真鍮製らしきリングの部分は、大きさの調節が可能になっている。
精一杯広げると、男としてはかなり細い亜鳥の指には、どうにかはめることができた。
「ほら、聡一郎。ものすごく綺麗」
屋台にぶら下がっている電球に、亜鳥は指輪をかざしてみせる。するとアクリルでできた玉飾りは、本物のように輝いて見えた。
しかしもっと輝いていたのは、それを心底嬉しそうに見つめる、亜鳥の瞳だと聡一郎は思う。
思わず「ください」と店主に言うと、亜鳥はますます眩しいほどの笑顔を見せる。
「俺ねえ、聡一郎。この指輪、うんと大事にするよ。それでこれから働いてお金を貯めたら、今度は俺が聡一郎に買ってあげるね」
多分亜鳥にとっては、本物もオモチャもどうでもいいことなのかもしれない。大切なのは、お互いが傍にいて、幸せだと感じることだと思っているに違いないからだ。
「ああ。楽しみにしてるぞ」
うなずいた聡一郎は、自分がオモチャの指輪をして飲みに行ったら、バーの常連たちもマスターもさぞ肝をつぶすだろうと考えて、思わず苦笑する。だが天使の笑みで指輪にキスを繰り返す亜鳥を見ていると、むしろその指輪になりたい、と思ってしまったのだった。
一覧へ戻る
そう言って亜鳥が袖を引っ張ったのは、初詣に訪れた神社の露店だった。聡一郎は品物が並べられた台の上を、眉を寄せて眺める。そこには亜鳥の年頃の青年が欲しがるようなものは、なにも乗っていなかったからだ。だが亜鳥の指先は、はっきりとひとつの商品を示している。
「お前まさか。これを結婚指輪にしたいとか思ってるんじゃねえだろうな」
それは空豆ほどの大きさの、アクリル製の青い宝石を模した飾りがついた、キラキラと光る指輪のオモチャだった。
「だって、絵本で見たのとすごく似てるよ」
「かもしれねえが、これは子供のオモチャだぞ。すぐ壊れちまうし、安物もいいとこだ」
「安いなら、高いよりいいじゃない」
それはそうかもしれないが、七百円は安すぎる。聡一郎としては、近いうちにきちんとした店でペアで名前を入れた、プラチナの指輪を用意しようと思っていたのだ。
亜鳥は紙で作られた箱から、指輪を手に取ってしげしげと眺めた。子供用のオモチャだから小さいが、ニッケルか真鍮製らしきリングの部分は、大きさの調節が可能になっている。
精一杯広げると、男としてはかなり細い亜鳥の指には、どうにかはめることができた。
「ほら、聡一郎。ものすごく綺麗」
屋台にぶら下がっている電球に、亜鳥は指輪をかざしてみせる。するとアクリルでできた玉飾りは、本物のように輝いて見えた。
しかしもっと輝いていたのは、それを心底嬉しそうに見つめる、亜鳥の瞳だと聡一郎は思う。
思わず「ください」と店主に言うと、亜鳥はますます眩しいほどの笑顔を見せる。
「俺ねえ、聡一郎。この指輪、うんと大事にするよ。それでこれから働いてお金を貯めたら、今度は俺が聡一郎に買ってあげるね」
多分亜鳥にとっては、本物もオモチャもどうでもいいことなのかもしれない。大切なのは、お互いが傍にいて、幸せだと感じることだと思っているに違いないからだ。
「ああ。楽しみにしてるぞ」
うなずいた聡一郎は、自分がオモチャの指輪をして飲みに行ったら、バーの常連たちもマスターもさぞ肝をつぶすだろうと考えて、思わず苦笑する。だが天使の笑みで指輪にキスを繰り返す亜鳥を見ていると、むしろその指輪になりたい、と思ってしまったのだった。