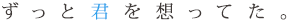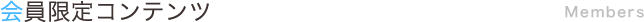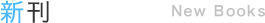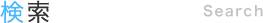どうしようもない恋
「それ、くれよ」
いきなり三隅に言われて、東宮はとまどった。高校二年の放課後、塾に行く前の時間調整をしつつ、教室で板チョコをかじっていた。それを、三隅に欲しいと言われたのだ。
「……いいけど」
そんなふうに、三隅に何かを頼まれることは滅多にない。内心の動揺を押し隠しつつ、東宮は自分が直接口をつけた部分を避けて、反対側からパキンと折った。
「はい」
銀紙に包まれたものを差し出しながら、三隅を眺める。毎日のようにその顔を見ているというのに、そのたびに感動するほど整った顔立ちだ。
「ありがと」
特に、にこっと笑ってくれたときの表情が好きだ。指先が触れあうだけでも淡い痺れが広がったのを隠すために、東宮はうつむいた。
それだけではなく耳がじんわりと赤くなったので、気付かれないために、早くいなくなってくれないかな、と思う。
その気持ちが態度にも現れて、上靴の先で軽く三隅の足を蹴った。
「邪魔だ。消えろ」
「はいはい」
三隅はくすくすと笑いながら、座っていた机から立ち上がる。
「おまえさ。今日が何の日だか、知ってる?」
謎かけのような言葉を残して、三隅は鞄をつかんで教室から消えた。今日はやけに大荷物だ。いつもの学生鞄に加えて、スポーツバックまで持っている。
廊下に出た三隅は、早速同級生から話しかけられていた。三隅以外にはほとんど友人のいない東宮とは違って、彼はいつでも誰かに囲まれている。
その賑やかな声が聞こえなくなるまで待ってから、東宮は全身から力を抜いた。
――今日は何の日?
その答えが、黒板の日時を見たことで不意に導き出された。二月十四日。
「そっか。……今日は、バレンタインデーだ」
男子校だというのに、去年の三隅は他校の女子から大量にチョコをもらっていた。今年もおそらく、そうだったのだろう。
なのにどうしてあの男は、東宮からのチョコを欲しがったのか。
嫌な予感を覚えて、背筋にざわざわと戦慄が走った。
絶対に見抜かれまいと隠し通していた恋心を、三隅は見抜いていたとでもいうのか。
密かに三隅に恋心を抱いている東宮からチョコをねだることで、おまえの気持ちはお見通しだとほのめかしてからかう。そんな残酷なところが、三隅にはあった。
東宮は板チョコをくわえたまま、パキンと折って口に運び、心の中でつぶやいてみる。
バカ。
大っ嫌いだ。
絶対に、この気持ちは隠し通してみせる。三隅にだけは、教えてやらない。
そんなふうに思うかたわらで、口の中に広がるチョコの味に、三隅とキスしているような甘さが広がる。
三隅の心をはかりかねて、振り回されるばかりの高校時代だった。
一覧へ戻る
いきなり三隅に言われて、東宮はとまどった。高校二年の放課後、塾に行く前の時間調整をしつつ、教室で板チョコをかじっていた。それを、三隅に欲しいと言われたのだ。
「……いいけど」
そんなふうに、三隅に何かを頼まれることは滅多にない。内心の動揺を押し隠しつつ、東宮は自分が直接口をつけた部分を避けて、反対側からパキンと折った。
「はい」
銀紙に包まれたものを差し出しながら、三隅を眺める。毎日のようにその顔を見ているというのに、そのたびに感動するほど整った顔立ちだ。
「ありがと」
特に、にこっと笑ってくれたときの表情が好きだ。指先が触れあうだけでも淡い痺れが広がったのを隠すために、東宮はうつむいた。
それだけではなく耳がじんわりと赤くなったので、気付かれないために、早くいなくなってくれないかな、と思う。
その気持ちが態度にも現れて、上靴の先で軽く三隅の足を蹴った。
「邪魔だ。消えろ」
「はいはい」
三隅はくすくすと笑いながら、座っていた机から立ち上がる。
「おまえさ。今日が何の日だか、知ってる?」
謎かけのような言葉を残して、三隅は鞄をつかんで教室から消えた。今日はやけに大荷物だ。いつもの学生鞄に加えて、スポーツバックまで持っている。
廊下に出た三隅は、早速同級生から話しかけられていた。三隅以外にはほとんど友人のいない東宮とは違って、彼はいつでも誰かに囲まれている。
その賑やかな声が聞こえなくなるまで待ってから、東宮は全身から力を抜いた。
――今日は何の日?
その答えが、黒板の日時を見たことで不意に導き出された。二月十四日。
「そっか。……今日は、バレンタインデーだ」
男子校だというのに、去年の三隅は他校の女子から大量にチョコをもらっていた。今年もおそらく、そうだったのだろう。
なのにどうしてあの男は、東宮からのチョコを欲しがったのか。
嫌な予感を覚えて、背筋にざわざわと戦慄が走った。
絶対に見抜かれまいと隠し通していた恋心を、三隅は見抜いていたとでもいうのか。
密かに三隅に恋心を抱いている東宮からチョコをねだることで、おまえの気持ちはお見通しだとほのめかしてからかう。そんな残酷なところが、三隅にはあった。
東宮は板チョコをくわえたまま、パキンと折って口に運び、心の中でつぶやいてみる。
バカ。
大っ嫌いだ。
絶対に、この気持ちは隠し通してみせる。三隅にだけは、教えてやらない。
そんなふうに思うかたわらで、口の中に広がるチョコの味に、三隅とキスしているような甘さが広がる。
三隅の心をはかりかねて、振り回されるばかりの高校時代だった。