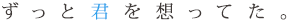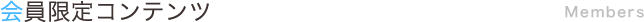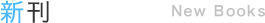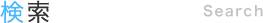うさ耳悪魔に振り回されて困ってます…!
「これは……アモン様、いらっしゃいませ。お連れの方は、もしや契約者の……?」
「うむ。弥千代だ」
阿門はうなずき、初めて入ったであろうバーの店内を、珍しそうに見回してきょろきょろしている弥千代をうながして、カウンター席に座らせた。
バーテンダーのジョンはグラスを手にしたまま固まり、まるで宇宙人でも見るような目で、ふたりを眺める。
「どうした。私の顔になにかついているか」
「い、いえ。ただ、アモン様がそうした服をお召しになっているところは、あまり見たことがなかったなと思いまして」
今日の阿門は、カジュアルなパーカーとデニムを着ていた。指摘された阿門は、自慢気に言う。
「いいだろう。今時のフードのついた服が欲しいと言ったら、弥千代が選んでくれたのだ。このスウェットという素材はなかなかいいな、軽くて着やすい。近代の服飾の進化というのは、大したものだな」
だがジャンは複雑な表情で、ぼそりとつぶやいた。
「信じられない。あの、すべてにおいて高級感と一流を望んでいた誇り高いアモン様が……」
「うん? なにか言ったか?」
「あ、いえ。こちらのことです」
「なあ、ジョン。このパーカーだが、私と弥千代のものはお揃いなのだ。ペアルックというのだそうだが、こうした格好をしたことがあるか?」
「……そ、そうなのですか。いえ、私には残念ながら、そうした機会がありませんもので」
「それは本当に残念だな。なあ、弥千代」
「もう、恥ずかしいよ阿門。そういうの、あんまり人に言わないで」
真っ赤になって俯いた弥千代の顎を、阿門はくいと持ちあげ、その唇にチュッと軽くキスをする。
「わっ、やめてよ、こんなとこで!」
「貴様が可愛らしい顔をするから悪い」
かつて人々の醜い悪行に歓喜していた、誇り高き悪魔のメロメロになっている姿に、もう見ていられないとジョンは眩暈を覚えた。
「と、ところで、ご注文はどうされますか」
「そうだな。弥千代はなにがいい」
「俺は弱いから。ジュースでいいよ」
「せっかくバーなのだから、酒にしろ。……ジョン。ここには、おでんと熱燗はないのか?」
えっ、とジョンは彫りの深い、整った顔の頬を引きつらせた。
「ざ、残念ですが、そうしたものは……」
「ちょっと、阿門。そんな無理を言ったら悪いだろ。俺は軽いカクテルをお願いします」
「貴様は優しいな、弥千代。本当に、こんな思いやり深い愛らしい生き物が周囲を不幸にするなど、まったく意味がわからん」
阿門はやるせないといった口調で言ったが、ジョンはこっそり内心で、これだけ見せつけられあてつけられて、すでに自分にも不幸が及んでいる、と考えていたのだった。
一覧へ戻る
「うむ。弥千代だ」
阿門はうなずき、初めて入ったであろうバーの店内を、珍しそうに見回してきょろきょろしている弥千代をうながして、カウンター席に座らせた。
バーテンダーのジョンはグラスを手にしたまま固まり、まるで宇宙人でも見るような目で、ふたりを眺める。
「どうした。私の顔になにかついているか」
「い、いえ。ただ、アモン様がそうした服をお召しになっているところは、あまり見たことがなかったなと思いまして」
今日の阿門は、カジュアルなパーカーとデニムを着ていた。指摘された阿門は、自慢気に言う。
「いいだろう。今時のフードのついた服が欲しいと言ったら、弥千代が選んでくれたのだ。このスウェットという素材はなかなかいいな、軽くて着やすい。近代の服飾の進化というのは、大したものだな」
だがジャンは複雑な表情で、ぼそりとつぶやいた。
「信じられない。あの、すべてにおいて高級感と一流を望んでいた誇り高いアモン様が……」
「うん? なにか言ったか?」
「あ、いえ。こちらのことです」
「なあ、ジョン。このパーカーだが、私と弥千代のものはお揃いなのだ。ペアルックというのだそうだが、こうした格好をしたことがあるか?」
「……そ、そうなのですか。いえ、私には残念ながら、そうした機会がありませんもので」
「それは本当に残念だな。なあ、弥千代」
「もう、恥ずかしいよ阿門。そういうの、あんまり人に言わないで」
真っ赤になって俯いた弥千代の顎を、阿門はくいと持ちあげ、その唇にチュッと軽くキスをする。
「わっ、やめてよ、こんなとこで!」
「貴様が可愛らしい顔をするから悪い」
かつて人々の醜い悪行に歓喜していた、誇り高き悪魔のメロメロになっている姿に、もう見ていられないとジョンは眩暈を覚えた。
「と、ところで、ご注文はどうされますか」
「そうだな。弥千代はなにがいい」
「俺は弱いから。ジュースでいいよ」
「せっかくバーなのだから、酒にしろ。……ジョン。ここには、おでんと熱燗はないのか?」
えっ、とジョンは彫りの深い、整った顔の頬を引きつらせた。
「ざ、残念ですが、そうしたものは……」
「ちょっと、阿門。そんな無理を言ったら悪いだろ。俺は軽いカクテルをお願いします」
「貴様は優しいな、弥千代。本当に、こんな思いやり深い愛らしい生き物が周囲を不幸にするなど、まったく意味がわからん」
阿門はやるせないといった口調で言ったが、ジョンはこっそり内心で、これだけ見せつけられあてつけられて、すでに自分にも不幸が及んでいる、と考えていたのだった。