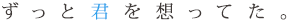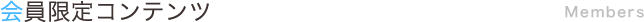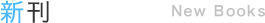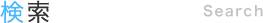誘惑のボディーガードと傷だらけの数学者
空港は冷房が効きすぎていて、信じられないほど寒かった。
震えながらアロハシャツの肩を摩る。今、「世界で一番寒い場所は?」と尋ねられたとしたら、僕は間違いなく、南の海のど真ん中、ブーゲンビリアが生い茂るこの空港だと答えるだろう。僕と深見さんは念願のバカンスを終え、今から家に帰るところだ。
深見さんと暮らすようになってから、僕は公共交通機関を使うことが昔ほど苦痛ではなくなった。学会への参加も増えた。今回の旅も学会からそのまま南の島へ直行するプランだったので、研究が頭から離れず、存分に楽しめないのではないかと思っていたが、そんな心配は必要なかった。深見さんと愛し合った後に閃いたアイディアを(なぜか、いつもそうなのだ。快感は脳を活性化させるのだろうか)ノートにいくつか書き留めたぐらいで、あとは数学を忘れて休暇を満喫した。
「使用機の到着遅れ……」
「まだ時間がありますね」
深見さんも僕の隣で電光掲示板を見上げている。
いつ聞いても惚れ惚れするようないい声だ。低くて少し掠れていて、なのに、しっとりしている。話しかけられただけで、ものすごく上手なやり方で首筋を撫でてもらっているような気分になれる。
声だけではなく、外見も素晴らしいとしか言いようがない。日に焼けた滑らかな肌、シャープな顔の輪郭、どこか乾いた風を感じさせるような髭、野生的な鋭さと艶やかさを併せ持っている目元、思慮深い内面が滲み出るような唇。
見上げるほど大きいのに、決してアンバランスには見えない鍛え上げられた身体も目を引いた。高い身体能力に裏打ちされた洗練された身のこなしが、それをさらに引き立てている。何もかもが一分の隙もなく整っていた。すれ違う誰もが一度は彼を盗み見る。空港のような場所では特に顕著だ。
深見さんも僕と同じように観光客向けの店で購入したアロハシャツを羽織っている。しかも、完全にジョークとして作られたであろう、いかれたサメ映画がモチーフのもので、彼自身も「いいですね、これ。俺にぴったり」と大笑いしていたというのに、だ。
なんでこんなにかっこいいんだろ。
目立つ柄のアロハシャツを着た深見さんは、髭や眉の傷跡も相まって、ちょっと怖い人みたいに見える。目が合ったら凄まれそうだ。この大男とやり合ったら絶対に敵わないだろうな、とほとんどの人が思うはずだ。
けれど、あまりに魅力的なので、皆、危険を承知でこっそりと目で追わずにはいられない。どんな格好をしていても、何をしていても、どこにいても様になる。
深見さんは本当に賢明で穏やかで、(彼自身は頑なに否定するけれど)少し心配になるぐらい優しい人だが、相当に近づかない限り、それは彼の見た目には表れない。
けれど間近で接すれば、明らかだ。
目が合った。深見さんの目尻がそれだけで、ふっと甘く緩む。どんなに回数を重ねても、僕は深見さんと目が合うたびに、何度だって彼に恋をしてしまう。
「さっさと荷物預けて、コーヒーでも飲みますか?」
深見さんはそう言うと、大きなトランクを軽々と片手で持ち上げ向きを変えた。もう片方の手には大量に紙袋を下げている。天羽さんや研究所の面々、深見さんの職場の人達、それから、兄さんへのお土産だ。兄さんは僕らがバカンスを計画していると知ると、「これでコーヒー豆を買ってこい」と僕に命令し、明らかにコーヒー豆の代金としては多過ぎる額を押し付けてきた。あれから兄さんも少し変わった。
ふと目に入った深見さんの褐色の太い腕は温かそうで、頼もしくて、寒さとは無縁に見えた。ひ弱な僕と違って、彼は全く寒さを感じていないのだろう。
「あ、う……うん」
僕は口の中で言葉を呑み込んだ。
深見さんは我慢強い人だった。もともと肉体が頑強というのもあるのかもしれないが、こちらから促さない限りは、滅多なことでは寒いとも暑いとも言わない。機嫌の悪さを人に悟らせないし、他人に対して寛容だ。この旅行中も彼が不平や不満を口にすることはなかった。
全く、ということはないか……。
いつも穏やかな彼が、きつく眉根を寄せて荒い息を吐き、咽び泣かんばかりに「もう駄目だ」「つらい」と訴えて、僕に縋り付くその様をつい思い出してしまう。
ホテルのベッドの甘い香りがする真っ白なシーツの上で、逞しい褐色の身体をくねらせる彼は素晴らしかった。
深見さんは普段は真面目そうに引き結んでいる唇を淫らに濡らして僕を頬張り、「早くこれをぶちこんでくれ」と何度も強請った。そして、たじろぐほど大きくて肉付きのいい、盛り上がった丸い尻を差し出す彼に「遅い」と叱られ、「焦らすな」と文句を言われた。
それでなくても正気を手放しそうだというのに、追い打ちをかけるように「いい」「もっと」と言って僕を煽りまくる深見さんに抗えず、快楽を貪りつくした。
それなのに深見さんは事後、僕を満足げに抱きしめ、彼の豊かな胸筋に頬を埋めさせながらこう言った。「やりすぎだ」「少しは加減しろ」。拗ねたような甘い声で詰られた。
ほんの数時間前にもしたことだが、思い出すだけで股間に血が集まってしまいそうだ。
いやいやいやいや、そうじゃない。
慌てて頭を振る。確かに深見さんは情事の際には僕にいろいろと要求するし、理不尽な不平も不満も言うが、なんというかあれは、むしろサービスというか、それを言う事で彼も解放され、僕は喜んで彼の言いなりになって、精根尽き果てるまで頑張ってしまうという、とにかく、普通の文句とは少し違うものだ。
ベッドの外での深見さんは僕に頼ることはない。僕の方が頼ってばかりいる。
深見さんのおかげで、この旅は本当に楽しくて快適だった。
二人で街をぶらぶらしていた時には、狙いすましたかのように面倒臭いタイミングで尿意を催した僕のために、深見さんは高級ブティックが建ち並ぶ通りで一緒にトイレを探してくれた。
その後、慣れないサンダルのせいで僕が靴擦れを作ったので、深見さんは予定を変更してレンタカーを借り、ドライブに連れ出してくれた。しかも彼は、いつの間にか星が綺麗に見える穴場を現地の人から聞き出していた。その夜は静かな高台で寝そべって、満天の星空を眺めた。お互いの指先や頬に唇で悪戯を仕掛けながら、他愛のない会話を楽しんだ。
伝統のダンスをショーとして見せる店に入った時に僕は、酒の入った若者達に絡まれそうになったが、深見さんが遠くから僕に呼びかけて笑っただけで、彼らは蜘蛛の子を散らすように去って行った。深見さんは声を荒らげる必要すらなかった。彼に喧嘩をふっかける勇気のある奴などそうはいない。
飲み物を持って悠然と席についた深見さんは、僕の肩を抱き寄せて言った。
「全く油断も隙もないな。まあ、誘いたくなるのは分かりますがね。南雲さんもちゃんと『恋人がいるから』って断ってくださいよ」
もちろん声をかけてきた彼らは僕と遊びたいわけではなかった。猫がネズミを見つけるように、いじめっ子がいじめられっ子を見つけただけだ。それなのに、彼のその一言によって、僕が情けない奴であるという事実も、彼らの悪意も、すっかりなかったことになってしまった。深見さんは、そういう気の使い方が本当に上手だった。
僕の靴擦れが治るのを見計らって、深見さんは僕をビーチへ誘った。混雑しているというほどではないが、思ったよりも人が多い。どっちを向いても人と目が合ってしまいそうで落ち着かなかった。皆、赤銅色に日焼けして、一年中このビーチに住んでいるような風体だが、僕だけは水着姿でも、まるで着替えの途中でいきなり砂浜に放り出されてしまったみたいに場違いだった。
隔絶された生態系を持つこの島では、カモメではなくて白いハトが海沿いを飛び回っている。磯の匂いもあまりしない。人を恐れず砂浜を歩くハトの方が僕よりもずっとこの場に馴染んでいた。
居心地悪そうに俯いている僕に気が付いているのかいないのか(いや、絶対に気が付いているだろう。深見さんはそういう人だ)深見さんはサーファーに声を掛け、彼の連れていた犬を撫で始めた。
笑いながら耳の垂れた黒い大型犬と戯れる深見さんの姿に見惚れ、思わず生唾を飲んだ。犬に首筋を舐められて深見さんがのけ反ると、犬の前足に付いた砂が、盛り上がった胸筋の上をはらはらと流れ落ちた。ああ、僕も犬になって深見さんを舐めまわしたい。
深見さんは犬の扱いも実に手慣れている。曰く「軍用犬を扱う訓練の賜物」だそうだが、僕は騙されない。深見さんの魅力が犬にも有効なのだろう。そうに決まっている。
深見さんに促されて恐る恐る犬の首筋を撫でた。嫌がらずにじっとしていてくれる。大抵の犬は僕のことを好きではないが、この犬はずいぶんと気前がいいようだ。きっと深見さんと一緒にいるせいだろう。飼い主のサーファーは笑いながらそれを見ていた。
いつの間にか居心地の悪さは消えていた。
僕達も少しだけ泳ぎ、パラソルの下に戻って海を眺めた。器用にサーフボードに乗って波に揺られている犬に深見さんと二人で拍手を送った。
「すごいなあ、ちゃんと乗ってる」
僕が呟くと深見さんは悪戯っぽく笑って、借りたサーフボードを手に立ち上がり、歩き出した。どこへ行くのかと慌てる僕に振り返った深見さんは子供のような笑顔だ。
「見ててください!」
サーファー達が海へ入っていく深見さんを目で追いかけた。新入りがどれぐらいやれるのか見てやろうという顔つきだった。
数十秒後、ちょっとした喝采がビーチに沸き起こった。
それほど大きな波ではなかったが、深見さんは誰よりも洗練された動きで波を乗りこなしていた。素人の僕が見てもはっきりと分かった。そして何より美しかった。こんなふうに身体が動かせたらきっと人生が楽しいだろうと思うほどに。僕は何もかも忘れてすっかり見入ってしまった。
「すごい!!」
「ははは、なかなかやるでしょ俺……なんて、これも軍の訓練のおかげですけど」
「本当にすごい。かっこよかった! 上手なんだね」
すごい、すごい、と興奮気味に繰り返していると、次第に深見さんの頬が赤くなっていく。よく見ると目も少し潤んでいる。
「まいった……な」
深見さんは目を逸らして照れ臭そうに頬を掻いた。
「南雲さんにいいとこ見せようと思って、ちょっとはしゃぎ過ぎました。ははは、やった」
素朴で善良な言い方に胸がいっぱいになってしまった。どんな場面もそつなく切り抜け、ビーチの視線を独り占めにしても平然としていた彼が、僕なんかの褒め言葉に照れて口籠もっているというのが、なんだか信じられなかった。
こんなすごい人が僕の恋人なんだな。
強くて、優しくて、頭がよくて、何でもできて、どこを取っても完璧で、僕とは違って、その気になれば誰とだって幸せになれる人が。
「……南雲さん?」
呼びかけられて我に返った。深見さんがじっとこっちを見ている。
そうだった。コーヒーを飲みながら出発までの時間を潰そうという話だった。温かいコーヒーを飲めば寒さも少しはましになるだろうか。
ちらりとトランクを見た。中には厚手のパーカーが入っている。こういう時のために深見さんに持たされたものだ。荷物を預ける前に中から取り出して着込みたい。
けど、面倒臭いって思われるかな。
深見さんがそんなことを考えたりするような人間でないのは分かっている。ただ、この場でトランクを開けるのに抵抗があるだけだ。他人の気持ちなんて全然分からないくせに、人目が気になる性質なのだ。
あっちの椅子がたくさんあるスペースに行けばトランクを開けても注目されずに済むかな。結構遠いな。深見さんを無駄に歩かせちゃうな。でも、風邪引いたらもっと深見さんを心配させる。迷惑になる。それでなくてもこの旅行ではずっとお世話になりっぱなしだ。これ以上、呆れられたくない。
「あ……と、その」
口籠もる僕を見て、深見さんはにやりと笑った。
「やめた」
「へ?」
「なんか俺、疲れちゃいました」
そう言ってすたすたと歩き出す。
「え!? ちょっ……待って」
慌てて後を追いながら真っ青になる。
疲れた? 僕といるのが? 面倒をかけるから? 気を使わせ過ぎてるから?
大きな背中を追いかけていると、いつの間にかソファーの並ぶスペースに来ていた。深見さんは、土産の紙袋を床に置くと、テキパキと僕の荷物を開け、パーカーを取り出した。
あ、と思う間もなく、抱き込まれるようにして、二人並んでソファーに座らされた。
「あー、さみい! 冷房効き過ぎですよね」
深見さんはサイズの大きいパーカーを僕の上に毛布のように掛けた、その中で、温かな長い腕が僕の冷え切った腕に絡む。素肌と素肌が触れ合う。ぞくぞくするような心地よさだった。突然のことに面食らっていると、ぎゅっと手を握られた。
「眠いんです。寒いし、疲れた」
深見さんは、僕の肩に頭を預け、頬を摺り寄せて目を閉じている。
なんだ、なんだ。一体どういうつもりだ。
深見さんの体温がじんわりと僕を温める。深見さんはうっすら笑っている。いつ見ても死ぬほどかっこよくて可愛い。深見さんの匂いがする。何の拷問だろうか。
煩悩に支配されそうになりながらも、頭の中の冷静な部分は卑屈な考えを止めない。
深見さんが寒いわけないじゃないか。
パーカーはほとんど僕にかけられている。深見さんの剥き出しになっている方の、日に焼けた腕は、いつも通り思わず舌を這わせたくなるほど滑らかで、鳥肌も立っていない。
猛烈に恥ずかしくなってきた。
つまり、僕はまた深見さんに気を使われてしまったのだ。
いつもこうだ。深見さんにこうして大事に扱われるのが嫌なわけではない。むしろ嬉しい。けれど不安になる。こんな僕といて本当に深見さんは満足できるのだろうか。深見さんと出会って昔よりはましになったとはいえ、僕は相変わらず、傲慢で視野が狭くて自己中心的で、そのくせ弱くて臆病で、数学以外のことに関しては気が回らない。
深見さんと同じぐらい行動的で体力もあって、社交的な人物と一緒なら、彼はもっと自由になれるはずなのだ。以前紹介してもらった深見さんの友達のグラハムさんもブーンさんも、タイプは全く違うが、こんな僕にも優しくてフレンドリーで、そしてタフな人達だった。
きっと僕は今酷い顔をしているだろう。無意識のうちにそれを深見さんから隠そうと、わずかに身じろぎした時だ。深見さんが目を開け、ちらりと横目でこちらを見た。
あ……。
深見さんの目はとろりと潤んでいた。僕と目が合うと艶っぽく微笑む。先ほどとは違って獲物を狙う獣のような、本能が剥き出しの笑顔だった。
深見さんの長い指先が僕の手の甲を誘うように撫でている。
寒い、疲れた、眠い……彼は普段ほとんど不平や不満を言わない。
ベッドの上、以外では。
気が付いた途端に、目の前が真っ赤になるような欲情に襲われ、寒さがどこかへ吹き飛んだ。今すぐ深見さんをソファーに押し倒して、彼のタンクトップを捲り上げたい。アロハシャツの下に腕を入れ、背筋の窪みや張り詰めた僧帽筋を指で楽しみ、盛り上がった胸筋に軽く歯を立て、涎で汚したい。逞しい身体を抱きしめて耳や首筋にキスしたい。
この旅行中も猿のように毎晩盛っていたというのに、欲望がとめどなく溢れてくる。
駄目だ駄目だ、何考えてるんだ。公共の場だろ。
深見さんはそんな僕の葛藤を見透かすように、僕の手を指で弄び続けている。こんなこと一つとっても腹が立つほど上手い。このままでは人前でみっともなく喘いでしまいそうだ。逃げようとすると耳元で囁かれた。
「駄目です、このまま」
「……っ」
なんて声を出すのか。こらえ切れずに息を詰めた。
たぶん、今の深見さんは、セックスの時の我儘な深見さんだ。
僕を気遣っているには違いないので、普段の彼でもあるわけだが。いや、そもそもそこに明確な区別なんてない。いつでも深見さんは深見さんだ。情事の最中だって彼が本気で僕を邪険に扱ったことなんてなかった。
一つはっきりしていることは、どちらの深見さんであっても、僕は彼を愛しているということだ。頭の毛からつま先に至るまで全て。
彼と釣り合うのか、負担になっていないか、もちろん気にはなるが、考えても仕方ない。僕は彼と一緒にいるためならどんなことでもするのだ。そう決めた。
傷ついて暗い目をしていた深見さんを思い出す。何もかも諦め、罪悪感で凍りついた悲しい笑顔も。
今の彼は満ち足りているように見える。煩わしそうな様子もない。苦しそうに「自分はサメ野郎だ」と言っていたのに、今は笑いながら自らサメの柄を選んで着ている。寝たふりをしながら、指先だけで僕を翻弄して、実に楽しそうだ。
劣等感に悩んでいるのが馬鹿らしく思えてきた。
空港で恋人とこっそり手を繋いでいるのだ。何を悩むことがある。思い切り、のぼせていればいい。それを通行人から隠す方法に悩む方がよほど有意義だ。
僕のモヤモヤなんか、どうでもいいな。本当にどうでもいい。
今、深見さんが幸せそうに見えること、それが全てだ。
縋り付いて離れない。深見さんが嫌だと言うまでは。
そして、もしも……もしも万が一、彼がまた悲しむことが起きそうな時は、その時は僕が絶対に阻止しよう。
決意を新たにした僕だが、さしあたっての問題は硬くなってしまった股間である。通行人にばれないように、そっとパーカーの裾を引っ張った。深見さんがそれに気が付いて、息だけで笑う。まったく、誰のせいだと思っているのか。
また、こうやって深見さんと旅行がしたいな。
心の底からそう思う。本当に楽しくていい旅だった。次はどこへ行こう。
昔と違って僕はもう、どこへでも行ける。
深見さんと二人で、どこへでも。
一覧へ戻る
震えながらアロハシャツの肩を摩る。今、「世界で一番寒い場所は?」と尋ねられたとしたら、僕は間違いなく、南の海のど真ん中、ブーゲンビリアが生い茂るこの空港だと答えるだろう。僕と深見さんは念願のバカンスを終え、今から家に帰るところだ。
深見さんと暮らすようになってから、僕は公共交通機関を使うことが昔ほど苦痛ではなくなった。学会への参加も増えた。今回の旅も学会からそのまま南の島へ直行するプランだったので、研究が頭から離れず、存分に楽しめないのではないかと思っていたが、そんな心配は必要なかった。深見さんと愛し合った後に閃いたアイディアを(なぜか、いつもそうなのだ。快感は脳を活性化させるのだろうか)ノートにいくつか書き留めたぐらいで、あとは数学を忘れて休暇を満喫した。
「使用機の到着遅れ……」
「まだ時間がありますね」
深見さんも僕の隣で電光掲示板を見上げている。
いつ聞いても惚れ惚れするようないい声だ。低くて少し掠れていて、なのに、しっとりしている。話しかけられただけで、ものすごく上手なやり方で首筋を撫でてもらっているような気分になれる。
声だけではなく、外見も素晴らしいとしか言いようがない。日に焼けた滑らかな肌、シャープな顔の輪郭、どこか乾いた風を感じさせるような髭、野生的な鋭さと艶やかさを併せ持っている目元、思慮深い内面が滲み出るような唇。
見上げるほど大きいのに、決してアンバランスには見えない鍛え上げられた身体も目を引いた。高い身体能力に裏打ちされた洗練された身のこなしが、それをさらに引き立てている。何もかもが一分の隙もなく整っていた。すれ違う誰もが一度は彼を盗み見る。空港のような場所では特に顕著だ。
深見さんも僕と同じように観光客向けの店で購入したアロハシャツを羽織っている。しかも、完全にジョークとして作られたであろう、いかれたサメ映画がモチーフのもので、彼自身も「いいですね、これ。俺にぴったり」と大笑いしていたというのに、だ。
なんでこんなにかっこいいんだろ。
目立つ柄のアロハシャツを着た深見さんは、髭や眉の傷跡も相まって、ちょっと怖い人みたいに見える。目が合ったら凄まれそうだ。この大男とやり合ったら絶対に敵わないだろうな、とほとんどの人が思うはずだ。
けれど、あまりに魅力的なので、皆、危険を承知でこっそりと目で追わずにはいられない。どんな格好をしていても、何をしていても、どこにいても様になる。
深見さんは本当に賢明で穏やかで、(彼自身は頑なに否定するけれど)少し心配になるぐらい優しい人だが、相当に近づかない限り、それは彼の見た目には表れない。
けれど間近で接すれば、明らかだ。
目が合った。深見さんの目尻がそれだけで、ふっと甘く緩む。どんなに回数を重ねても、僕は深見さんと目が合うたびに、何度だって彼に恋をしてしまう。
「さっさと荷物預けて、コーヒーでも飲みますか?」
深見さんはそう言うと、大きなトランクを軽々と片手で持ち上げ向きを変えた。もう片方の手には大量に紙袋を下げている。天羽さんや研究所の面々、深見さんの職場の人達、それから、兄さんへのお土産だ。兄さんは僕らがバカンスを計画していると知ると、「これでコーヒー豆を買ってこい」と僕に命令し、明らかにコーヒー豆の代金としては多過ぎる額を押し付けてきた。あれから兄さんも少し変わった。
ふと目に入った深見さんの褐色の太い腕は温かそうで、頼もしくて、寒さとは無縁に見えた。ひ弱な僕と違って、彼は全く寒さを感じていないのだろう。
「あ、う……うん」
僕は口の中で言葉を呑み込んだ。
深見さんは我慢強い人だった。もともと肉体が頑強というのもあるのかもしれないが、こちらから促さない限りは、滅多なことでは寒いとも暑いとも言わない。機嫌の悪さを人に悟らせないし、他人に対して寛容だ。この旅行中も彼が不平や不満を口にすることはなかった。
全く、ということはないか……。
いつも穏やかな彼が、きつく眉根を寄せて荒い息を吐き、咽び泣かんばかりに「もう駄目だ」「つらい」と訴えて、僕に縋り付くその様をつい思い出してしまう。
ホテルのベッドの甘い香りがする真っ白なシーツの上で、逞しい褐色の身体をくねらせる彼は素晴らしかった。
深見さんは普段は真面目そうに引き結んでいる唇を淫らに濡らして僕を頬張り、「早くこれをぶちこんでくれ」と何度も強請った。そして、たじろぐほど大きくて肉付きのいい、盛り上がった丸い尻を差し出す彼に「遅い」と叱られ、「焦らすな」と文句を言われた。
それでなくても正気を手放しそうだというのに、追い打ちをかけるように「いい」「もっと」と言って僕を煽りまくる深見さんに抗えず、快楽を貪りつくした。
それなのに深見さんは事後、僕を満足げに抱きしめ、彼の豊かな胸筋に頬を埋めさせながらこう言った。「やりすぎだ」「少しは加減しろ」。拗ねたような甘い声で詰られた。
ほんの数時間前にもしたことだが、思い出すだけで股間に血が集まってしまいそうだ。
いやいやいやいや、そうじゃない。
慌てて頭を振る。確かに深見さんは情事の際には僕にいろいろと要求するし、理不尽な不平も不満も言うが、なんというかあれは、むしろサービスというか、それを言う事で彼も解放され、僕は喜んで彼の言いなりになって、精根尽き果てるまで頑張ってしまうという、とにかく、普通の文句とは少し違うものだ。
ベッドの外での深見さんは僕に頼ることはない。僕の方が頼ってばかりいる。
深見さんのおかげで、この旅は本当に楽しくて快適だった。
二人で街をぶらぶらしていた時には、狙いすましたかのように面倒臭いタイミングで尿意を催した僕のために、深見さんは高級ブティックが建ち並ぶ通りで一緒にトイレを探してくれた。
その後、慣れないサンダルのせいで僕が靴擦れを作ったので、深見さんは予定を変更してレンタカーを借り、ドライブに連れ出してくれた。しかも彼は、いつの間にか星が綺麗に見える穴場を現地の人から聞き出していた。その夜は静かな高台で寝そべって、満天の星空を眺めた。お互いの指先や頬に唇で悪戯を仕掛けながら、他愛のない会話を楽しんだ。
伝統のダンスをショーとして見せる店に入った時に僕は、酒の入った若者達に絡まれそうになったが、深見さんが遠くから僕に呼びかけて笑っただけで、彼らは蜘蛛の子を散らすように去って行った。深見さんは声を荒らげる必要すらなかった。彼に喧嘩をふっかける勇気のある奴などそうはいない。
飲み物を持って悠然と席についた深見さんは、僕の肩を抱き寄せて言った。
「全く油断も隙もないな。まあ、誘いたくなるのは分かりますがね。南雲さんもちゃんと『恋人がいるから』って断ってくださいよ」
もちろん声をかけてきた彼らは僕と遊びたいわけではなかった。猫がネズミを見つけるように、いじめっ子がいじめられっ子を見つけただけだ。それなのに、彼のその一言によって、僕が情けない奴であるという事実も、彼らの悪意も、すっかりなかったことになってしまった。深見さんは、そういう気の使い方が本当に上手だった。
僕の靴擦れが治るのを見計らって、深見さんは僕をビーチへ誘った。混雑しているというほどではないが、思ったよりも人が多い。どっちを向いても人と目が合ってしまいそうで落ち着かなかった。皆、赤銅色に日焼けして、一年中このビーチに住んでいるような風体だが、僕だけは水着姿でも、まるで着替えの途中でいきなり砂浜に放り出されてしまったみたいに場違いだった。
隔絶された生態系を持つこの島では、カモメではなくて白いハトが海沿いを飛び回っている。磯の匂いもあまりしない。人を恐れず砂浜を歩くハトの方が僕よりもずっとこの場に馴染んでいた。
居心地悪そうに俯いている僕に気が付いているのかいないのか(いや、絶対に気が付いているだろう。深見さんはそういう人だ)深見さんはサーファーに声を掛け、彼の連れていた犬を撫で始めた。
笑いながら耳の垂れた黒い大型犬と戯れる深見さんの姿に見惚れ、思わず生唾を飲んだ。犬に首筋を舐められて深見さんがのけ反ると、犬の前足に付いた砂が、盛り上がった胸筋の上をはらはらと流れ落ちた。ああ、僕も犬になって深見さんを舐めまわしたい。
深見さんは犬の扱いも実に手慣れている。曰く「軍用犬を扱う訓練の賜物」だそうだが、僕は騙されない。深見さんの魅力が犬にも有効なのだろう。そうに決まっている。
深見さんに促されて恐る恐る犬の首筋を撫でた。嫌がらずにじっとしていてくれる。大抵の犬は僕のことを好きではないが、この犬はずいぶんと気前がいいようだ。きっと深見さんと一緒にいるせいだろう。飼い主のサーファーは笑いながらそれを見ていた。
いつの間にか居心地の悪さは消えていた。
僕達も少しだけ泳ぎ、パラソルの下に戻って海を眺めた。器用にサーフボードに乗って波に揺られている犬に深見さんと二人で拍手を送った。
「すごいなあ、ちゃんと乗ってる」
僕が呟くと深見さんは悪戯っぽく笑って、借りたサーフボードを手に立ち上がり、歩き出した。どこへ行くのかと慌てる僕に振り返った深見さんは子供のような笑顔だ。
「見ててください!」
サーファー達が海へ入っていく深見さんを目で追いかけた。新入りがどれぐらいやれるのか見てやろうという顔つきだった。
数十秒後、ちょっとした喝采がビーチに沸き起こった。
それほど大きな波ではなかったが、深見さんは誰よりも洗練された動きで波を乗りこなしていた。素人の僕が見てもはっきりと分かった。そして何より美しかった。こんなふうに身体が動かせたらきっと人生が楽しいだろうと思うほどに。僕は何もかも忘れてすっかり見入ってしまった。
「すごい!!」
「ははは、なかなかやるでしょ俺……なんて、これも軍の訓練のおかげですけど」
「本当にすごい。かっこよかった! 上手なんだね」
すごい、すごい、と興奮気味に繰り返していると、次第に深見さんの頬が赤くなっていく。よく見ると目も少し潤んでいる。
「まいった……な」
深見さんは目を逸らして照れ臭そうに頬を掻いた。
「南雲さんにいいとこ見せようと思って、ちょっとはしゃぎ過ぎました。ははは、やった」
素朴で善良な言い方に胸がいっぱいになってしまった。どんな場面もそつなく切り抜け、ビーチの視線を独り占めにしても平然としていた彼が、僕なんかの褒め言葉に照れて口籠もっているというのが、なんだか信じられなかった。
こんなすごい人が僕の恋人なんだな。
強くて、優しくて、頭がよくて、何でもできて、どこを取っても完璧で、僕とは違って、その気になれば誰とだって幸せになれる人が。
「……南雲さん?」
呼びかけられて我に返った。深見さんがじっとこっちを見ている。
そうだった。コーヒーを飲みながら出発までの時間を潰そうという話だった。温かいコーヒーを飲めば寒さも少しはましになるだろうか。
ちらりとトランクを見た。中には厚手のパーカーが入っている。こういう時のために深見さんに持たされたものだ。荷物を預ける前に中から取り出して着込みたい。
けど、面倒臭いって思われるかな。
深見さんがそんなことを考えたりするような人間でないのは分かっている。ただ、この場でトランクを開けるのに抵抗があるだけだ。他人の気持ちなんて全然分からないくせに、人目が気になる性質なのだ。
あっちの椅子がたくさんあるスペースに行けばトランクを開けても注目されずに済むかな。結構遠いな。深見さんを無駄に歩かせちゃうな。でも、風邪引いたらもっと深見さんを心配させる。迷惑になる。それでなくてもこの旅行ではずっとお世話になりっぱなしだ。これ以上、呆れられたくない。
「あ……と、その」
口籠もる僕を見て、深見さんはにやりと笑った。
「やめた」
「へ?」
「なんか俺、疲れちゃいました」
そう言ってすたすたと歩き出す。
「え!? ちょっ……待って」
慌てて後を追いながら真っ青になる。
疲れた? 僕といるのが? 面倒をかけるから? 気を使わせ過ぎてるから?
大きな背中を追いかけていると、いつの間にかソファーの並ぶスペースに来ていた。深見さんは、土産の紙袋を床に置くと、テキパキと僕の荷物を開け、パーカーを取り出した。
あ、と思う間もなく、抱き込まれるようにして、二人並んでソファーに座らされた。
「あー、さみい! 冷房効き過ぎですよね」
深見さんはサイズの大きいパーカーを僕の上に毛布のように掛けた、その中で、温かな長い腕が僕の冷え切った腕に絡む。素肌と素肌が触れ合う。ぞくぞくするような心地よさだった。突然のことに面食らっていると、ぎゅっと手を握られた。
「眠いんです。寒いし、疲れた」
深見さんは、僕の肩に頭を預け、頬を摺り寄せて目を閉じている。
なんだ、なんだ。一体どういうつもりだ。
深見さんの体温がじんわりと僕を温める。深見さんはうっすら笑っている。いつ見ても死ぬほどかっこよくて可愛い。深見さんの匂いがする。何の拷問だろうか。
煩悩に支配されそうになりながらも、頭の中の冷静な部分は卑屈な考えを止めない。
深見さんが寒いわけないじゃないか。
パーカーはほとんど僕にかけられている。深見さんの剥き出しになっている方の、日に焼けた腕は、いつも通り思わず舌を這わせたくなるほど滑らかで、鳥肌も立っていない。
猛烈に恥ずかしくなってきた。
つまり、僕はまた深見さんに気を使われてしまったのだ。
いつもこうだ。深見さんにこうして大事に扱われるのが嫌なわけではない。むしろ嬉しい。けれど不安になる。こんな僕といて本当に深見さんは満足できるのだろうか。深見さんと出会って昔よりはましになったとはいえ、僕は相変わらず、傲慢で視野が狭くて自己中心的で、そのくせ弱くて臆病で、数学以外のことに関しては気が回らない。
深見さんと同じぐらい行動的で体力もあって、社交的な人物と一緒なら、彼はもっと自由になれるはずなのだ。以前紹介してもらった深見さんの友達のグラハムさんもブーンさんも、タイプは全く違うが、こんな僕にも優しくてフレンドリーで、そしてタフな人達だった。
きっと僕は今酷い顔をしているだろう。無意識のうちにそれを深見さんから隠そうと、わずかに身じろぎした時だ。深見さんが目を開け、ちらりと横目でこちらを見た。
あ……。
深見さんの目はとろりと潤んでいた。僕と目が合うと艶っぽく微笑む。先ほどとは違って獲物を狙う獣のような、本能が剥き出しの笑顔だった。
深見さんの長い指先が僕の手の甲を誘うように撫でている。
寒い、疲れた、眠い……彼は普段ほとんど不平や不満を言わない。
ベッドの上、以外では。
気が付いた途端に、目の前が真っ赤になるような欲情に襲われ、寒さがどこかへ吹き飛んだ。今すぐ深見さんをソファーに押し倒して、彼のタンクトップを捲り上げたい。アロハシャツの下に腕を入れ、背筋の窪みや張り詰めた僧帽筋を指で楽しみ、盛り上がった胸筋に軽く歯を立て、涎で汚したい。逞しい身体を抱きしめて耳や首筋にキスしたい。
この旅行中も猿のように毎晩盛っていたというのに、欲望がとめどなく溢れてくる。
駄目だ駄目だ、何考えてるんだ。公共の場だろ。
深見さんはそんな僕の葛藤を見透かすように、僕の手を指で弄び続けている。こんなこと一つとっても腹が立つほど上手い。このままでは人前でみっともなく喘いでしまいそうだ。逃げようとすると耳元で囁かれた。
「駄目です、このまま」
「……っ」
なんて声を出すのか。こらえ切れずに息を詰めた。
たぶん、今の深見さんは、セックスの時の我儘な深見さんだ。
僕を気遣っているには違いないので、普段の彼でもあるわけだが。いや、そもそもそこに明確な区別なんてない。いつでも深見さんは深見さんだ。情事の最中だって彼が本気で僕を邪険に扱ったことなんてなかった。
一つはっきりしていることは、どちらの深見さんであっても、僕は彼を愛しているということだ。頭の毛からつま先に至るまで全て。
彼と釣り合うのか、負担になっていないか、もちろん気にはなるが、考えても仕方ない。僕は彼と一緒にいるためならどんなことでもするのだ。そう決めた。
傷ついて暗い目をしていた深見さんを思い出す。何もかも諦め、罪悪感で凍りついた悲しい笑顔も。
今の彼は満ち足りているように見える。煩わしそうな様子もない。苦しそうに「自分はサメ野郎だ」と言っていたのに、今は笑いながら自らサメの柄を選んで着ている。寝たふりをしながら、指先だけで僕を翻弄して、実に楽しそうだ。
劣等感に悩んでいるのが馬鹿らしく思えてきた。
空港で恋人とこっそり手を繋いでいるのだ。何を悩むことがある。思い切り、のぼせていればいい。それを通行人から隠す方法に悩む方がよほど有意義だ。
僕のモヤモヤなんか、どうでもいいな。本当にどうでもいい。
今、深見さんが幸せそうに見えること、それが全てだ。
縋り付いて離れない。深見さんが嫌だと言うまでは。
そして、もしも……もしも万が一、彼がまた悲しむことが起きそうな時は、その時は僕が絶対に阻止しよう。
決意を新たにした僕だが、さしあたっての問題は硬くなってしまった股間である。通行人にばれないように、そっとパーカーの裾を引っ張った。深見さんがそれに気が付いて、息だけで笑う。まったく、誰のせいだと思っているのか。
また、こうやって深見さんと旅行がしたいな。
心の底からそう思う。本当に楽しくていい旅だった。次はどこへ行こう。
昔と違って僕はもう、どこへでも行ける。
深見さんと二人で、どこへでも。