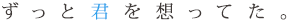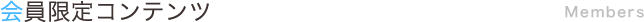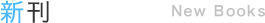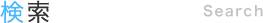いけ好かない商売敵と
どうにか今日提出だった浮気レポートの作成を終えて、朝生は大きく息をついた。
ざっと見返してから、請求書とあわせて電子メールで送る。以前は郵送が多かったが、電子メールのほうが依頼人にとって秘密の保持がしやすいケースもあるそうだから、人によって使い分けることにしている。
一仕事終えはしたものの、まだ仕事は山積みだった。徹夜だったからこのまま眠りたかったが、今日も今日とて仕事がある。疲れ切った身体で立ち上がり、コーヒーでも飲んでしゃっきりしようと給湯室に向かった。コーヒーメーカーからコーヒーをカップに移して一口飲んだところで、ハッとした。
――これが、泥みたいなコーヒーか……!
朝生がオーナーを務めるこの雑居ビルの、店子である法律事務所の松本弁護士から、そんなふうにののしられたことを思い出す。松本に直接このコーヒーを振る舞ったことはなかったはずだが、あの男はいったいどこでその情報を仕入れたのだろうか。そのことが話のネタとして上がるのも当然だと思えるほどの、泥水加減をようやく自分自身で体感した。
何時間前にセットしたか覚えてないコーヒーは、煮詰まりすぎてどろどろだ。粉もスーパーで安売りしていたものを適当に買っていたから、そもそもがあまり美味ではないのだ。
――それに引き替え、あいつのところのはおいしかった。
朝生にこのコーヒーのことを「泥水」と言い切った、ムカつく弁護士のことを思い出す。
そのときには猛烈に反発する気持ちが湧いたものだが、自身で納得した今となってはさほど腹が立たない。
それどころか、疲れているせいもあって猛烈にカフェインを摂取したくなり、朝生はその弁護士の事務所に押しかけることにした。
どうせ事務所は廊下を挟んで向かいだし、あの律儀な弁護士は午前中から事務所にいる。今もおそらく、優雅なコーヒーブレイクの最中だろう。
そう思うとコーヒーが飲みたい中毒のようになって泥水が入っていた自分のマグカップとコーヒーメーカーを洗い、そのまま向かいの法律事務所に押しかける。
さすがに客がいたら遠慮しようと思ったが、こんな早い時間からでは客はいないようだったので無言で入りこみ、給湯室に直行する。
給湯室と言っても、小さなシンクと冷蔵庫があるだけの小さなスペースだ。そこにコーヒーメーカーがあって、いい匂いをさせているものとばかり思っていた朝生は、それを探して視線をさまよわせた。
――コーヒーメーカーどこ? 俺のコーヒーは?
「何か用?」
無言で入ってきた朝生をただ目で見送っていた松本だったが、さすがに気になってやってきたようだ。背後から声をかけられて、朝生は振り返った。
「いや、コーヒーあったらもらおうと思って。コーヒーメーカーってねえのかよ?」
「うちはお客さんがいたら、一杯ずつ淹れる方針だから。コーヒー飲みたいのか?」
言われて、朝生はうなずいた。
「余ってたら、もらおうと思っただけだけど」
「余ってはいないけど、淹れてやる」
「いちいち一杯ずつ淹れてるの?」
「おまえみたいに、朝どかっと作っておくと煮詰まるばかりだろ。そういうところがガサツなんだよ。座ってろ。持っていくから」
面倒だという気配を全身から漂わせてはいたが、わりと親切な男らしい。
そんなふうに言われて、朝生はソファに戻った。あのおいしいコーヒーが飲めるのだと思うと、自然と浮かれていく自分に気づく。
――あれ? 俺、そんなコーヒー好きじゃなかったはずだけど。
それでも、おいしいものはおいしい。松本のコーヒーは格別だ。しばらくすると松本がやってきて、朝生の前にせんべいの袋菓子を二つ置いてくれた。お茶菓子までもらえるとは思ってなくて、目を見開いた後に朝生はありがたくいただくことにする。お菓子は自分で買うことはないだけに、たまに食べるそれがおいしく感じられた。徹夜の身体に、外側の糖衣部分の甘さが染みていく。
そのうちに戻ってきた松本が、持参したマグカップに入ったコーヒーをテーブルに置いてくれた。
それを口に運んだ朝生は、その香り高さにしみじみとため息をついた。コーヒーの味などろくに気にせずに生きてきたが、格別においしい。それに、ここは居心地が良かった。松本の事務所で、ここには他ならぬ松本がいるというのが大問題だったが、ソファの座り心地はいいし、コーヒーとお茶菓子までつくなんて最高だ。自分が顧客だったら、まずはこの歓待に心が浮き立つ。
「うちも、……多少はサービスしないとな。いつまでも泥水コーヒーを出していたんじゃ……」
「おまえのところじゃ、発泡酒サービスがあるって聞いたことがあるぞ」
松本も一休みすることにしたのか、自分の分も淹れたコーヒーを持って向かいに腰掛けてくる。形良く組んだ長い足を見せつけられながら、朝生はコーヒーを口に運んだ。
「俺が飲みたいときに客がくると、一緒に飲むんだけどさ。男性客はそれで満足してくれるけど、女性客には引かれることが多い」
「だろうな」
「けど、うちはわりと女性客で持ってるところもあるから」
「愛想でも売ろうってか。泥水コーヒーが多少はマシになったところで、所詮は付け焼き刃だ」
クールに言い切られて、朝生はカチンときた。こんなふうに経営努力をしなければならないと思うようになったのは、自分の探偵事務所の真ん前に、同じく「ストーカー対策」を項目に掲げている法律事務所が出来たせいだ。
それがなければ、客には困っていなかったはずだ。
だからこそ、つい松本に向かって毒を吐いた。
「――コーヒーのおいしさで多少を誤魔化したところで、客が判断するのはそいつの仕事に満足するかどうかだから」
「へええ? そんなことを、泥水コーヒーを出す探偵にわざわざレクチャーされるとは思わなかったよ」
「てめえ!」
毒には毒を、で言い返されて、朝生は立ち上がった。松本も同じように立ち上がると思ったが、フンと盛大に鼻を鳴らした後で横柄にあごをしゃくってきた。
「泥水コーヒーよりも、客の心証を良くするためには大切なことがある。それが何だか知りたいか?」
こんな男に勿体ぶられながら教えてもらうのは癪だったから、思いっきり無愛想な顔で言い返してみた。
「何だ?」
「笑顔だ」
「笑顔ォ? 愛想良くしてるだろ、俺は」
思わぬ返事が返ってきて、朝生は仰天した。
ことさら客に愛想悪くしている自覚はない。松本相手ならともかく、むしろ客には格別にこやかにしている自覚さえあったのだ。
だが、それでは合格をもらえないらしい。
「おまえのそれが愛想良いものだとしたら、コンビニの渋谷くんは極上の愛想良しってことになる」
コンビニの渋谷くんというのは、二人の間でも話題になるほど、愛想のなさが目につく従業員だった。彼よりも自分は愛想が悪いのかと、さすがに驚く。
「俺、そのレベル?」
「自覚がないとは驚きだな」
「でも、多少は愛想よくしてると思うけど」
「なはずないだろ。まず初回の客が来たとき、おまえは『こいつはちゃんと金を持ってるのかな』って値踏みしているように目を細める。その顔が、凶悪さと邪悪さに満ちている」
「そりゃ、金払えるかどうかの値踏みはするけど、邪悪ってほどじゃ……」
言い訳しようとしたが、朝生は途中で言葉を呑みこんだ。主観はともかく、客観的には松本が指摘したように見えるのかもしれない。
仕事を引き受けてそれなりに親しくなった客が「怖い人だと思ってました」と言ってくることがあるし、初見で引かれてそのままドアを閉じられることもある。
そんなことが重なっていただけに、頭から否定はできない。
どうすればいいんだ、と松本に目で尋ねると、したり顔で言ってきた。
「俺相手に、笑顔の練習をしてみたらどうだ? 廊下で顔を合わせるたびに、にこやかに挨拶してみろ」
「何で、てめえなんかに。それこそ、コンビニの渋谷くんに笑顔で挨拶したほうがマシだ」
「渋谷くんに毎朝にこやかに挨拶をしてると、そのうち、かすかに笑ってくれるようになるぞ」
「本当か?」
「まぁ、渋谷くんでもいい。試してみろ」
その提案に、朝生はしばし考えた。
まずはそういうところから始めるのも悪くないのかもしれない。女性客は口コミを広めてくれるというし、今後のことを考えれば、女性客をより獲得し、心証を良くしておくのに損なことは何もない。
だが、試しに少し口角を緩めてみただけで、松本がコーヒーを吹き出さんがばかりに反応したので、いきりたって立ち上がった。
「てめええええ!」
「悪い悪かった悪かった。笑わないから、もう一度やってみろ」
「もうしねえよ」
ふてくされて、朝生は空になったマグカップをつかんだ。
「――だけど、コーヒーのおいしい淹れかた教えて」
松本に教えを乞うのは癪だったが、コーヒーの味は認める。経営努力はまずはこの一歩からだ。だけど、松本は立ち上がろうとはしなかった。
「飲みたくなったときに、うち来れば」
「へ?」
「お代は、笑顔一回でいい」
何でこのムカつく男が、こんな朝生にとってお得なだけの交換条件を出してくるのかわからない。
目が合うと柔らかく微笑まれ、気のあるまなざしを送りこまれてドキッとする。
前回の事件のとき、この男と関係を持ったときのことを思い出した。あれから、ことさら素っ気なく振る舞う日々が続いている。何もかもなかったことにしてしまいたかったけれども、何かしらの未練を感じているのは朝生のほうなのかもしれない。
「ざけんな。誰がてめえのために笑うかよ」
それだけ言い捨てて、マグカップを持って部屋を出てしまった。だがコーヒーが飲みたいときにいつでも行ってもいいんだと思うと、少し頬が緩んだ。
――また何か、一緒にできるような仕事がないかなぁ。
そんなふうに思い始めている自分の頬を、ぴしゃっと軽く叩く。
あんな男と、関係を深めたいわけでは決してない。だけど、時間が経つにつれてだんだんとその日々が、懐かしく切ないもののように思えてくるから不思議だった。
一覧へ戻る
ざっと見返してから、請求書とあわせて電子メールで送る。以前は郵送が多かったが、電子メールのほうが依頼人にとって秘密の保持がしやすいケースもあるそうだから、人によって使い分けることにしている。
一仕事終えはしたものの、まだ仕事は山積みだった。徹夜だったからこのまま眠りたかったが、今日も今日とて仕事がある。疲れ切った身体で立ち上がり、コーヒーでも飲んでしゃっきりしようと給湯室に向かった。コーヒーメーカーからコーヒーをカップに移して一口飲んだところで、ハッとした。
――これが、泥みたいなコーヒーか……!
朝生がオーナーを務めるこの雑居ビルの、店子である法律事務所の松本弁護士から、そんなふうにののしられたことを思い出す。松本に直接このコーヒーを振る舞ったことはなかったはずだが、あの男はいったいどこでその情報を仕入れたのだろうか。そのことが話のネタとして上がるのも当然だと思えるほどの、泥水加減をようやく自分自身で体感した。
何時間前にセットしたか覚えてないコーヒーは、煮詰まりすぎてどろどろだ。粉もスーパーで安売りしていたものを適当に買っていたから、そもそもがあまり美味ではないのだ。
――それに引き替え、あいつのところのはおいしかった。
朝生にこのコーヒーのことを「泥水」と言い切った、ムカつく弁護士のことを思い出す。
そのときには猛烈に反発する気持ちが湧いたものだが、自身で納得した今となってはさほど腹が立たない。
それどころか、疲れているせいもあって猛烈にカフェインを摂取したくなり、朝生はその弁護士の事務所に押しかけることにした。
どうせ事務所は廊下を挟んで向かいだし、あの律儀な弁護士は午前中から事務所にいる。今もおそらく、優雅なコーヒーブレイクの最中だろう。
そう思うとコーヒーが飲みたい中毒のようになって泥水が入っていた自分のマグカップとコーヒーメーカーを洗い、そのまま向かいの法律事務所に押しかける。
さすがに客がいたら遠慮しようと思ったが、こんな早い時間からでは客はいないようだったので無言で入りこみ、給湯室に直行する。
給湯室と言っても、小さなシンクと冷蔵庫があるだけの小さなスペースだ。そこにコーヒーメーカーがあって、いい匂いをさせているものとばかり思っていた朝生は、それを探して視線をさまよわせた。
――コーヒーメーカーどこ? 俺のコーヒーは?
「何か用?」
無言で入ってきた朝生をただ目で見送っていた松本だったが、さすがに気になってやってきたようだ。背後から声をかけられて、朝生は振り返った。
「いや、コーヒーあったらもらおうと思って。コーヒーメーカーってねえのかよ?」
「うちはお客さんがいたら、一杯ずつ淹れる方針だから。コーヒー飲みたいのか?」
言われて、朝生はうなずいた。
「余ってたら、もらおうと思っただけだけど」
「余ってはいないけど、淹れてやる」
「いちいち一杯ずつ淹れてるの?」
「おまえみたいに、朝どかっと作っておくと煮詰まるばかりだろ。そういうところがガサツなんだよ。座ってろ。持っていくから」
面倒だという気配を全身から漂わせてはいたが、わりと親切な男らしい。
そんなふうに言われて、朝生はソファに戻った。あのおいしいコーヒーが飲めるのだと思うと、自然と浮かれていく自分に気づく。
――あれ? 俺、そんなコーヒー好きじゃなかったはずだけど。
それでも、おいしいものはおいしい。松本のコーヒーは格別だ。しばらくすると松本がやってきて、朝生の前にせんべいの袋菓子を二つ置いてくれた。お茶菓子までもらえるとは思ってなくて、目を見開いた後に朝生はありがたくいただくことにする。お菓子は自分で買うことはないだけに、たまに食べるそれがおいしく感じられた。徹夜の身体に、外側の糖衣部分の甘さが染みていく。
そのうちに戻ってきた松本が、持参したマグカップに入ったコーヒーをテーブルに置いてくれた。
それを口に運んだ朝生は、その香り高さにしみじみとため息をついた。コーヒーの味などろくに気にせずに生きてきたが、格別においしい。それに、ここは居心地が良かった。松本の事務所で、ここには他ならぬ松本がいるというのが大問題だったが、ソファの座り心地はいいし、コーヒーとお茶菓子までつくなんて最高だ。自分が顧客だったら、まずはこの歓待に心が浮き立つ。
「うちも、……多少はサービスしないとな。いつまでも泥水コーヒーを出していたんじゃ……」
「おまえのところじゃ、発泡酒サービスがあるって聞いたことがあるぞ」
松本も一休みすることにしたのか、自分の分も淹れたコーヒーを持って向かいに腰掛けてくる。形良く組んだ長い足を見せつけられながら、朝生はコーヒーを口に運んだ。
「俺が飲みたいときに客がくると、一緒に飲むんだけどさ。男性客はそれで満足してくれるけど、女性客には引かれることが多い」
「だろうな」
「けど、うちはわりと女性客で持ってるところもあるから」
「愛想でも売ろうってか。泥水コーヒーが多少はマシになったところで、所詮は付け焼き刃だ」
クールに言い切られて、朝生はカチンときた。こんなふうに経営努力をしなければならないと思うようになったのは、自分の探偵事務所の真ん前に、同じく「ストーカー対策」を項目に掲げている法律事務所が出来たせいだ。
それがなければ、客には困っていなかったはずだ。
だからこそ、つい松本に向かって毒を吐いた。
「――コーヒーのおいしさで多少を誤魔化したところで、客が判断するのはそいつの仕事に満足するかどうかだから」
「へええ? そんなことを、泥水コーヒーを出す探偵にわざわざレクチャーされるとは思わなかったよ」
「てめえ!」
毒には毒を、で言い返されて、朝生は立ち上がった。松本も同じように立ち上がると思ったが、フンと盛大に鼻を鳴らした後で横柄にあごをしゃくってきた。
「泥水コーヒーよりも、客の心証を良くするためには大切なことがある。それが何だか知りたいか?」
こんな男に勿体ぶられながら教えてもらうのは癪だったから、思いっきり無愛想な顔で言い返してみた。
「何だ?」
「笑顔だ」
「笑顔ォ? 愛想良くしてるだろ、俺は」
思わぬ返事が返ってきて、朝生は仰天した。
ことさら客に愛想悪くしている自覚はない。松本相手ならともかく、むしろ客には格別にこやかにしている自覚さえあったのだ。
だが、それでは合格をもらえないらしい。
「おまえのそれが愛想良いものだとしたら、コンビニの渋谷くんは極上の愛想良しってことになる」
コンビニの渋谷くんというのは、二人の間でも話題になるほど、愛想のなさが目につく従業員だった。彼よりも自分は愛想が悪いのかと、さすがに驚く。
「俺、そのレベル?」
「自覚がないとは驚きだな」
「でも、多少は愛想よくしてると思うけど」
「なはずないだろ。まず初回の客が来たとき、おまえは『こいつはちゃんと金を持ってるのかな』って値踏みしているように目を細める。その顔が、凶悪さと邪悪さに満ちている」
「そりゃ、金払えるかどうかの値踏みはするけど、邪悪ってほどじゃ……」
言い訳しようとしたが、朝生は途中で言葉を呑みこんだ。主観はともかく、客観的には松本が指摘したように見えるのかもしれない。
仕事を引き受けてそれなりに親しくなった客が「怖い人だと思ってました」と言ってくることがあるし、初見で引かれてそのままドアを閉じられることもある。
そんなことが重なっていただけに、頭から否定はできない。
どうすればいいんだ、と松本に目で尋ねると、したり顔で言ってきた。
「俺相手に、笑顔の練習をしてみたらどうだ? 廊下で顔を合わせるたびに、にこやかに挨拶してみろ」
「何で、てめえなんかに。それこそ、コンビニの渋谷くんに笑顔で挨拶したほうがマシだ」
「渋谷くんに毎朝にこやかに挨拶をしてると、そのうち、かすかに笑ってくれるようになるぞ」
「本当か?」
「まぁ、渋谷くんでもいい。試してみろ」
その提案に、朝生はしばし考えた。
まずはそういうところから始めるのも悪くないのかもしれない。女性客は口コミを広めてくれるというし、今後のことを考えれば、女性客をより獲得し、心証を良くしておくのに損なことは何もない。
だが、試しに少し口角を緩めてみただけで、松本がコーヒーを吹き出さんがばかりに反応したので、いきりたって立ち上がった。
「てめええええ!」
「悪い悪かった悪かった。笑わないから、もう一度やってみろ」
「もうしねえよ」
ふてくされて、朝生は空になったマグカップをつかんだ。
「――だけど、コーヒーのおいしい淹れかた教えて」
松本に教えを乞うのは癪だったが、コーヒーの味は認める。経営努力はまずはこの一歩からだ。だけど、松本は立ち上がろうとはしなかった。
「飲みたくなったときに、うち来れば」
「へ?」
「お代は、笑顔一回でいい」
何でこのムカつく男が、こんな朝生にとってお得なだけの交換条件を出してくるのかわからない。
目が合うと柔らかく微笑まれ、気のあるまなざしを送りこまれてドキッとする。
前回の事件のとき、この男と関係を持ったときのことを思い出した。あれから、ことさら素っ気なく振る舞う日々が続いている。何もかもなかったことにしてしまいたかったけれども、何かしらの未練を感じているのは朝生のほうなのかもしれない。
「ざけんな。誰がてめえのために笑うかよ」
それだけ言い捨てて、マグカップを持って部屋を出てしまった。だがコーヒーが飲みたいときにいつでも行ってもいいんだと思うと、少し頬が緩んだ。
――また何か、一緒にできるような仕事がないかなぁ。
そんなふうに思い始めている自分の頬を、ぴしゃっと軽く叩く。
あんな男と、関係を深めたいわけでは決してない。だけど、時間が経つにつれてだんだんとその日々が、懐かしく切ないもののように思えてくるから不思議だった。