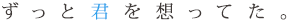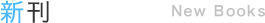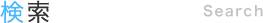「私は己の嫁を、幸せにしたいのだ」
病に倒れた兄を救うため神である炎珠の嫁になった砂羽。
それから二年。砂羽は絵を生業にしながら衣食住のすべてを炎珠に世話してもらっていた。
身体を交え気を渡す存在が神にとっての「嫁」と言われているのに、炎珠はとにかく砂羽を甘やかし、楽しいことも気持ちいいことも
与えられてばかり。
このままでは炎珠に見捨てられてしまうのでは!? 危機感を抱いた砂羽は炎珠を喜ばせられるしっかりとした奥さんになるために、孤軍奮闘し始めるけれど……?
オンライン書店
電子書店
登場人物紹介
-

- 稲城砂羽(いなしろ さわ)
幼いころ、周りの人々の顔が蛇に見えていたせいで、孤独な日々を過ごしていた。おっとりした性格で、家事などが一切できないが絵を描く才能がある。
-

- 炎珠天(えんじゅてん)
砂羽の暮らす地域一帯の土地神。砂羽をところん甘やかして溺愛している。神さまなのに家事が得意なようで――。
試し読み
「炎珠。今日のこの玉子焼き、すごく美味しいです。ふっくらして、優しい甘さで」
広大な古く広い屋敷。
欄間には雲を模した細かな飾りが彫り込まれ、時代を感じさせるとともに、贅を尽くして建築されたことをうかがわせた。
その二十畳ばかりある居間で、分厚い檜の座卓を挟み、砂羽の正面に座った炎珠は満足そうに応じる。
「そうか。実は今回、マヨネーズとやらいう代物を入れてみたのだが、正解だったらしいな。日々、俗世について学んできた成果だ」
なるほど、と砂羽はうなずくと、次にほかほかと炊けている白米に箸を伸ばした。が、口に届く前にぽろりと零れてしまう。
「あっ。ごめんなさい……ああっ」
慌てた砂羽は、今度は茶碗をひっくり返してしまった。
「落ち着け、砂羽。お代わりならいくらでもある」
穏やかな表情で炎珠は言うと、長い指をぱちりと鳴らした。
するとその指先から髪と同じく赤い、小さな炎に蛙の足がついたような玉が十匹ばかりも生まれ、座卓の上をよちよちとこちらに歩いてくる。
これが初めてのことではないので、驚きはしないのだが、何度見ても不思議な生き物たちだなあと、砂羽は感心して彼らを眺めた。それを炎珠が、苦笑しつつたしなめる。
「小物の使役者どもなど気にせず、ちゃんと箸を見なさい。また零してしまうぞ」
「あ。はい」
砂羽は応じたものの、赤い玉たちが零れた米粒をゴミ箱に運び、御櫃から茶碗に新しい白米を盛る様子から、なかなか目を離せずにいた。
それから顔を上げ、改めて目の前の炎珠をしげしげと見つめる。
──もう見慣れているはずなのに、こんな力を使える炎珠って、やっぱりすごいな。
それもそのはず、艶やかな赤い髪と知的で品のある容貌、すらりとした肢体を持つ上に、玉子焼きにマヨネーズを入れて一工夫してくれる炎珠の正体は、人間ではなかった。この地域一帯の土地神だったのだ。
そしてその神様の花嫁が、稲城砂羽。
この大きな屋敷の世帯主であり、まともに箸もつかえない、二十歳になったばかりの画家だった。
砂羽が炎珠の花嫁になったのは、今から二年ほど前のことになる。
当時の砂羽は高校三年生だったのだが、毎日が辛く、孤独で、寂しかった。それはもう、幼少時から、ずっとだ。
これは古株の家政婦から聞かされた話だが、自分が生まれる以前に、裏庭の蔵を壊した際、大きな蛇を殺してしまい、その祟りが一族を襲ったのだという。
そのころちょうど、砂羽は母親のお腹の中にいた。
両親は、そろって同じ蛇の夢を見て、まずはお腹の赤ん坊から祟ってやると言われたらしい。
そのせいかどうかはわからないが、母親は砂羽を産み落として間もなく、亡くなってしまった。そして乳母に育てられた砂羽は、その乳母にも父親にも二歳年上の兄にも、家政婦にも懐かなかった。
なぜなら物心ついたときから、全ての人間たちが、蛇に見えるようになっていたからだ。
言葉はわかる。けれど表情は真っ赤な舌がちろちろとのぞくばかりで、判然としない。
鏡を見れば、自分だけが他のものたちと姿が違う。強烈な疎外感と孤独と恐怖の中、砂羽は絵を描くことに、わずかな救いを見出していた。
そしてもうひとつ、心の支えにしていたことがある。それは裏庭とは別の、母屋に面した大きな庭にある石の祠だ。
この祠には、きっと神さまが住んでいるに違いない、と本能的に感じた砂羽は、ときには祠に話しかけ、願掛けをし、その間だけは心の安らぎを得るようになっていた。
そして十八歳の、初夏のある日。
砂羽の孤独な日々は、唐突に終わりを告げることになる。
事態が進展したきっかけは砂羽ではなく、兄である羽須美だった。
大学で倒れた兄の病は原因不明であり、長期間の入院にもかかわらず容態は悪化していく。
そんな中、砂羽の父親はどういうわけか、急に庭の祠を綺麗にし始めた。
必死の形相で、苔と鳥のフンだらけだった祠を掃除し、榊を飾り、御神酒を供え、ついには休日の午後に近隣の神社の神主を引っ張って来て、なにやら祈念を頼んだらしい。
「……あの。ちょっと、聞いていいですか。この祠にいるのがなんの神さまなのか、知っ
ていますか」
蛇の姿を恐れ、滅多に他人に話しかけることなどない砂羽だったが、このときだけは好奇心を抑えきれずに、庭にいた神主と思おぼしき装束の人物に尋ねてみた。
すると神主は、他の人間たちと同様の蛇の顔をこちらに向け、親切に教えてくれた。
「もちろん、知っているよ。もとは、この村で旅の僧侶を助けたとき、礼にと貰った赤い瑪瑙を田に埋めたところ、大変に実り豊かな土地となったということで、後に瑪瑙を掘り返して、祠にお祀りしたのが始まりと伝えられているんだ」
へえ、と砂羽は、幼いころ遊び場として馴染んでいた石の祠に、尊敬の眼差しを向けた。
「で、でも、それならどうして、ずっと放ってあったんでしょう」
時代だろうねえ、としみじみとした声で神主は言う。
「昔は、村長だったこちらの稲城家を中心に、祭礼の儀式もあったらしいけれどね。簡略化され、形骸化し、そのうちに手を合わせるものもいなくなってしまったんだろう。まあ、特に珍しいことではないよ」
そういうものなのか、と砂羽は納得して、そっと神主の傍を離れた。
どうやら砂羽の父親は、跡継ぎである長男の命が脅かされるという危機に至って、放っておいた土地神の存在を思い出し、蛇の呪いを祓うため、利用しようと考えたらしい。
「祠におわします我らが土地神さま。どうか貴方にお仕えする一族を、蛇の呪いからお救
いください」
神主の横で深く首を垂れ、手を合わせて祈る砂羽の父親は、上等の絹のスーツを身に着け、白いものが混じり始めた頭を、深々と下げている。
──怖くて厳しいお父さんがあんなことをするの、初めて見た。
砂羽は庭の杉の木の陰から、そっとこの様子を見守っていた。
自分の誕生と引き換えに伴侶を失ってしまったせいか、父親が砂羽を疎んじていると常々感じていたため、なるべく視界に入らないほうがいいだろう、と思ったのだ。
父親はなおも、神経質そうな額に筋を立て、祈りの言葉を口にし続けていた。
「願いを叶えてくださったなら、ここにもっと立派な祠を作りなおします。金に糸目はつけず、豪華な社にしますので。供え物も、酒蔵から取り寄せた名酒を捧げます。どうか、お聞き届けください」
その必死な口調に、砂羽も思わず首を垂れ、祠に向かって両手を合わせていた。そっと目を閉じて俯き、小さく唇を動かす。
──どうか、お兄さんが、元気になりますように。お父さんの願いが、叶いますように。
誰も、悲しい思いをしませんように。
父親からも兄からも愛情を向けられていない砂羽だったが、家族を大事に思う心はある。
そして祈りを終え、顔を上げたまさにそのとき。
「……ならばその願い、聞き届けよう」
すい、と祠から炎のような人影が現れ、砂羽は大きく目を見開いた。
手前の池の水面に、わずかに浮いて立った炎珠を見て、うわあ! と悲鳴を上げたのは神主だ。
父親も目を?む き、口を大きく開いたまま、硬直したようになっている。
みんなより少し高い位置に浮いたまま、人型の炎は口を開いた。
「私の名は炎珠天。お前たちも知っているように、この祠に祀られた土地神だ」
とても信じられないことだが、現に目の前にいる存在は、どこからどう見ても超常現象としか言いようのないものだった。
「炎珠。今日のこの玉子焼き、すごく美味しいです。ふっくらして、優しい甘さで」
広大な古く広い屋敷。
欄間には雲を模した細かな飾りが彫り込まれ、時代を感じさせるとともに、贅を尽くして建築されたことをうかがわせた。
その二十畳ばかりある居間で、分厚い檜の座卓を挟み、砂羽の正面に座った炎珠は満足そうに応じる。
「そうか。実は今回、マヨネーズとやらいう代物を入れてみたのだが、正解だったらしいな。日々、俗世について学んできた成果だ」
なるほど、と砂羽はうなずくと、次にほかほかと炊けている白米に箸を伸ばした。が、口に届く前にぽろりと零れてしまう。
「あっ。ごめんなさい……ああっ」
慌てた砂羽は、今度は茶碗をひっくり返してしまった。
「落ち着け、砂羽。お代わりならいくらでもある」
穏やかな表情で炎珠は言うと、長い指をぱちりと鳴らした。
するとその指先から髪と同じく赤い、小さな炎に蛙の足がついたような玉が十匹ばかりも生まれ、座卓の上をよちよちとこちらに歩いてくる。
これが初めてのことではないので、驚きはしないのだが、何度見ても不思議な生き物たちだなあと、砂羽は感心して彼らを眺めた。それを炎珠が、苦笑しつつたしなめる。
「小物の使役者どもなど気にせず、ちゃんと箸を見なさい。また零してしまうぞ」
「あ。はい」
砂羽は応じたものの、赤い玉たちが零れた米粒をゴミ箱に運び、御櫃から茶碗に新しい白米を盛る様子から、なかなか目を離せずにいた。
それから顔を上げ、改めて目の前の炎珠をしげしげと見つめる。
──もう見慣れているはずなのに、こんな力を使える炎珠って、やっぱりすごいな。
それもそのはず、艶やかな赤い髪と知的で品のある容貌、すらりとした肢体を持つ上に、玉子焼きにマヨネーズを入れて一工夫してくれる炎珠の正体は、人間ではなかった。この地域一帯の土地神だったのだ。
そしてその神様の花嫁が、稲城砂羽。
この大きな屋敷の世帯主であり、まともに箸もつかえない、二十歳になったばかりの画家だった。
砂羽が炎珠の花嫁になったのは、今から二年ほど前のことになる。
当時の砂羽は高校三年生だったのだが、毎日が辛く、孤独で、寂しかった。それはもう、幼少時から、ずっとだ。
これは古株の家政婦から聞かされた話だが、自分が生まれる以前に、裏庭の蔵を壊した際、大きな蛇を殺してしまい、その祟りが一族を襲ったのだという。
そのころちょうど、砂羽は母親のお腹の中にいた。
両親は、そろって同じ蛇の夢を見て、まずはお腹の赤ん坊から祟ってやると言われたらしい。
そのせいかどうかはわからないが、母親は砂羽を産み落として間もなく、亡くなってしまった。そして乳母に育てられた砂羽は、その乳母にも父親にも二歳年上の兄にも、家政婦にも懐かなかった。
なぜなら物心ついたときから、全ての人間たちが、蛇に見えるようになっていたからだ。
言葉はわかる。けれど表情は真っ赤な舌がちろちろとのぞくばかりで、判然としない。
鏡を見れば、自分だけが他のものたちと姿が違う。強烈な疎外感と孤独と恐怖の中、砂羽は絵を描くことに、わずかな救いを見出していた。
そしてもうひとつ、心の支えにしていたことがある。それは裏庭とは別の、母屋に面した大きな庭にある石の祠だ。
この祠には、きっと神さまが住んでいるに違いない、と本能的に感じた砂羽は、ときには祠に話しかけ、願掛けをし、その間だけは心の安らぎを得るようになっていた。
そして十八歳の、初夏のある日。
砂羽の孤独な日々は、唐突に終わりを告げることになる。
事態が進展したきっかけは砂羽ではなく、兄である羽須美だった。
大学で倒れた兄の病は原因不明であり、長期間の入院にもかかわらず容態は悪化していく。
そんな中、砂羽の父親はどういうわけか、急に庭の祠を綺麗にし始めた。
必死の形相で、苔と鳥のフンだらけだった祠を掃除し、榊を飾り、御神酒を供え、ついには休日の午後に近隣の神社の神主を引っ張って来て、なにやら祈念を頼んだらしい。
「……あの。ちょっと、聞いていいですか。この祠にいるのがなんの神さまなのか、知っ
ていますか」
蛇の姿を恐れ、滅多に他人に話しかけることなどない砂羽だったが、このときだけは好奇心を抑えきれずに、庭にいた神主と思おぼしき装束の人物に尋ねてみた。
すると神主は、他の人間たちと同様の蛇の顔をこちらに向け、親切に教えてくれた。
「もちろん、知っているよ。もとは、この村で旅の僧侶を助けたとき、礼にと貰った赤い瑪瑙を田に埋めたところ、大変に実り豊かな土地となったということで、後に瑪瑙を掘り返して、祠にお祀りしたのが始まりと伝えられているんだ」
へえ、と砂羽は、幼いころ遊び場として馴染んでいた石の祠に、尊敬の眼差しを向けた。
「で、でも、それならどうして、ずっと放ってあったんでしょう」
時代だろうねえ、としみじみとした声で神主は言う。
「昔は、村長だったこちらの稲城家を中心に、祭礼の儀式もあったらしいけれどね。簡略化され、形骸化し、そのうちに手を合わせるものもいなくなってしまったんだろう。まあ、特に珍しいことではないよ」
そういうものなのか、と砂羽は納得して、そっと神主の傍を離れた。
どうやら砂羽の父親は、跡継ぎである長男の命が脅かされるという危機に至って、放っておいた土地神の存在を思い出し、蛇の呪いを祓うため、利用しようと考えたらしい。
「祠におわします我らが土地神さま。どうか貴方にお仕えする一族を、蛇の呪いからお救
いください」
神主の横で深く首を垂れ、手を合わせて祈る砂羽の父親は、上等の絹のスーツを身に着け、白いものが混じり始めた頭を、深々と下げている。
──怖くて厳しいお父さんがあんなことをするの、初めて見た。
砂羽は庭の杉の木の陰から、そっとこの様子を見守っていた。
自分の誕生と引き換えに伴侶を失ってしまったせいか、父親が砂羽を疎んじていると常々感じていたため、なるべく視界に入らないほうがいいだろう、と思ったのだ。
父親はなおも、神経質そうな額に筋を立て、祈りの言葉を口にし続けていた。
「願いを叶えてくださったなら、ここにもっと立派な祠を作りなおします。金に糸目はつけず、豪華な社にしますので。供え物も、酒蔵から取り寄せた名酒を捧げます。どうか、お聞き届けください」
その必死な口調に、砂羽も思わず首を垂れ、祠に向かって両手を合わせていた。そっと目を閉じて俯き、小さく唇を動かす。
──どうか、お兄さんが、元気になりますように。お父さんの願いが、叶いますように。
誰も、悲しい思いをしませんように。
父親からも兄からも愛情を向けられていない砂羽だったが、家族を大事に思う心はある。
そして祈りを終え、顔を上げたまさにそのとき。
「……ならばその願い、聞き届けよう」
すい、と祠から炎のような人影が現れ、砂羽は大きく目を見開いた。
手前の池の水面に、わずかに浮いて立った炎珠を見て、うわあ! と悲鳴を上げたのは神主だ。
父親も目を?む き、口を大きく開いたまま、硬直したようになっている。
みんなより少し高い位置に浮いたまま、人型の炎は口を開いた。
「私の名は炎珠天。お前たちも知っているように、この祠に祀られた土地神だ」
とても信じられないことだが、現に目の前にいる存在は、どこからどう見ても超常現象としか言いようのないものだった。