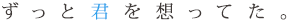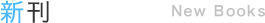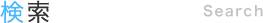雪弥は11年ぶりに耀と再会する。かつて雪弥の心をズタズタに切り裂いた傲慢な幼馴染だ。
だが、「君が好きなんだ、いまも」そう穏やかに囁いてくる目の前の耀に、雪弥は強烈な違和感を覚える。
記憶の中の耀とはまるで別人なのだ。そして連れて行かれたマンションで――。
「もう一度、お前をこんなふうにしたかった」態度を豹変させ、
雪弥をベッドにくくりつけて嗤う彼は、まさしく雪弥がよく知る耀で…!?
沙野風結子の初期の名作が新イラスト・改稿のうえ新装版で登場!
オンライン書店
電子書店
登場人物紹介
-

- 瀬口雪弥(せぐちゆきや)
連続暴行事件を追っている所轄の刑事。ある過去のできごとで、なにに対しても感情が動かないようになってしまった。
-

- 葛城耀(かつらぎよう)
雪弥の幼馴染。11年ぶりに再会すると、かつての彼とは違う雰囲気をまとっていて――。
試し読み
──この十一年間、僕の身体に、心に、なまなましく触れる人はいなかった。誰かの温かな手は肌に感じる「重み」でしかなく、誰かの温かな気遣いの言葉は「音の羅列」でしかなかった。
「すげぇ、後味悪いなぁ…」
吐き出すような呻きに、精巧な機械のようにキーボードを叩いていた指を止めて、瀬口雪弥は長い睫を上げた。切れ長の黒目勝ちな──というよりは、まるで目のなかを黒く塗り潰したような瞳で、向かいのデスクを見る。
大きな身体を椅子に深く預け、ネクタイをだらしなく緩めたスーツ姿の三十路の男。彼の眉間には皺が刻みこまれている。
「報告書は僕が上げておきますから、保高さんは帰って休んでください」
そう告げて、またキーボードのうえで指を動かしはじめると、保高がデスクに両肘をついて覗きこんできた。
「なぁ、瀬口さぁ。お前、無理しなくていいんだぞ」
「無理なんてしてません」
「……あんまり感情を溜めこんでっと、爆発するか壊れるかして、もたなくなるぞ」
「大丈夫です。自分なりに発散させてますから」
保高と組んで仕事をするようになってから一年。
こんな遣り取りを何度繰り返したか知れない。
保高は組まされた新米刑事が潰れないようにと気遣っているのだろうが、それは雪弥にとっては本当に不要なことだった。
「でも、今日のなんか発散させて飛ばせるようなモンじゃねぇだろ……あんな──なぁ」
さっぱりした長さの髪をぐしゃぐしゃにしながら保高が頭を?き毟しる。
……数時間前の出来事だ。
雪弥は保高とともに、指名手配中の強盗犯を追っていた。
容疑者は二十七歳無職の男で、一ヶ月前に薬局に押し入り、出刃包丁で薬剤師を刺して現金百五十万円を奪って逃走中だった。警察は行方を追っていたが、昨日、管内のパチンコ店にここ数日、容疑者らしき男が出入りしているという通報が店員によってもたらされた。
それで張り込みをしていたところ、午後になってふらりと容疑者が現れた。パチンコ店の入り口で声をかけると、男は脱だっ兎と のごとく逃げだした。
雪弥たちもまた、歩道の通行人のあいだを縫って全力疾走で容疑者を追った。
こういう狩りに慣れている刑事と、不摂生な容疑者との体力差は歴然としていた。あっという間に、間合いが詰まる。雪弥の伸ばした手が、容疑者の羽織ったダウンジャケットの裾を?んだ。引っ張る。
容疑者が、肩越しに血走った眼で雪弥を睨みつけた。
恐慌状態に顔面を引き攣つ らせた容疑者は、次の瞬間、ジャケットを脱ぎ捨てると、ガードレールへとスニーカーの靴裏を載せた。飛びかかる保高の手をすり抜けて、男はガードレール
を踏み越え、車道へと跳ぶ。
車の激しいクラクション。
タイヤが地面を擦る、甲高いブレーキ音。
ドン…という重い衝突音。
容疑者の身体は、あらぬ方向に手足を曲げて、まるで壊れたマネキンのように冬の空を飛んだ。
雪弥のすぐ横で、保高が言葉にならない呻き声を漏 らす。
雪弥は一拍も置かずに冷たいガードレールに手をついた。黒いコートを翻して飛び越え、車道へと降りる。道路に転がっている容疑者のもとに走り寄り、スラックスの膝が血に濡れるのも気にせずにアスファルトに跪く。
男の口から鳴るヒューヒューという小さな呼吸音を確かめ、携帯電話で救急車を呼んだ。
容疑者は、いまも生死の境を彷徨っている。
キーボードを打つ手を止めて、雪弥はまだ頭を?き毟っている保高に声をかけた。
「あれは事故ですよ。僕たちは自分の仕事をしただけです」
保高がのろりと顔を上げた。奥二重の目で雪弥を見詰める。
そして、苦笑を滲ませた。
「普通それは、先輩刑事の俺がヒヨッコのお前に言うセリフじゃないのか?」
「そうかもしれません」
保高は太い溜め息をひとつつくと上体を起こした。まるで容疑者の取り調べをするときのように、男っぽい爽やかな顔を引き締め、胸の前で腕を組んで訊いてきた。
「お前は、いまも……あの現場でのときも、なんでそんなに平然としてるんだ? 自分が追い詰めたせいで容疑者とはいえ、人ひとり死ぬかもしれないんだぞ。それについて思うところはないのか?」
人がましい反応をしないことを詰られるのは、この十一年間ですっかり慣れてしまった。普段は冷血漢だ人非人だと言われない程度に取り繕っているが、いざというとき本性は隠せないものだ。
「課長からは、冷静さが長所だと言われました」
黒いガラス玉の眼で保高を見返す。
先に視線を揺らしたのは保高のほうだった。
苦笑するように目を眇すがめて、決まり悪げに言う。
「お前のこと、ずっとなにかに似てる似てると思ってたんだが、いま思い出した。実家の日本人形だ」
日本人形のようだという形容は、雪弥には耳に馴染んだものだった。
「怖いぐらい綺麗な人形で、黒い着物に金の帯締めて、肩口に色糸巻いた鼓つづみを持ってるんだ。芸妓なんだろうが、愛想のない毅然とした細面で、そのくせこう立ち姿がそそる感じでな……。一度、ガラスケースから出そうとして、おふくろに怒られたっけ」
「出して、どうするつもりだったんですか?」
雪弥が尋ねると、保高がおどけたように口角を軽く下げた。
「ちょっと、着物の裾からなかを覗きたかったんだろうな。小学生のころの話だ」
「保高さんらしいですね」
唇を軽く綻ばせて、雪弥は答えた──保高が犯人の命についてどう思うか、というところから話題を逸らしてくれたことに肩の力を緩めながら。
そうしてふたたび、自分たちが生死の狭間へと追い詰めた男についての概要をパソコンに打ちこんでいく。
高校中退後、アルバイトを転々として生きてきた、社会に不適応感をいだいていたという二十七歳の男。二十七歳とは、雪弥と同い年だ。
年齢という共通項を見つけたからといって、心が痛むこともない。
……正確に言えば、なにに対しても鮮明に感情が動かないのだ。それこそ、ガラスケースのなかから世界を見ているかのように。
誰も、自分にじかに触れることはない。
なにごとも、自分の心を動かすことはない。
喜びも怒りも哀しみも愉しみも、自分のなかになまなましく湧き上がることはなかった。
「通してください。警察です」
夜の繁華街、脇道を覗きこんで幾重にも輪を作っている野次馬を?き分け、雪弥は路地へと抜けた。派出所の制服警官たちはすでに到着していて、現場の保全と被害者を宥めるのに懸命になっている。救急車はまだ来ていなかった。
「保高刑事!」
若い警官が保高の顔を見て、ほっとした表情をする。
「被害者はパニック状態になってます……腕は折れているかもしれません」
「わかった。瀬口は通報してきた奴の話を聞いてくれ」
雪弥は白い手袋を嵌は めながら頷いた。
保高が制服警官と交代して、被害者の若者──大学生ぐらいのようだ──の前に片膝をつく。
若者は首を必死に横に振って、尻をついたまま後ずさろうとする。
「落ち着け。もう大丈夫だからな」
温かくて力強い声だ。
「お、俺がなにしたっつーんだよっ? 歩いて……歩いてた、だけなのに、あいつ、なんなんだよぉっっ!?」
「ああ。歩いてただけなのに、怖い目にあったな」
保高が若者のジーンズの膝を力づけるように手で?む。
宥められて少しずつ落ち着きはじめた若者が、回らない呂律で喋りだす。
「袋──後ろから紙袋被せ、られてっ! け、蹴られて、硬い靴ですげぇ蹴られて、腕を、俺の腕をっ…………」
雪弥のほうは、被害者を見つけて警察に連絡してくれた会社勤めの女性からひととおり話を聞いたが、彼女は犯人の姿は見ていなかった。
──一月に入って、二件。十二月からの累計では五件か。
後ろから紙袋を被せて被害者の視界を奪ってから力任せに蹴りつける。ぐったりしたところで、うつ伏せにし、左の二の腕を踏んで固定して、外側に捩ね じり折る。
まったく同じ手口の通り魔事件が五件も起きているのだ。犯行は、決まって水曜日の夜。
犯人の姿を見た者はいない。
手帳をしまいながら、雪弥はふと動きを止めた。
視線。
自分の横顔に当てられている視線を感じる。
──なんだろう。この感じは……。
厚く埃を被った古い記憶を刺激される。
雪弥は黒髪をパッと散らして顔を上げた。野次馬のほうへと視線を飛ばす。
そして、睫の動きひとつも止まる。
野次馬たちのなかに、一際背の高い男の姿があった。品のいい濃紺のコートを羽織ったスー
ツ姿、二十代後半の精悍で華やかな顔立ちをした男だ。眼と髪の色は茶褐色。
まっすぐに、ふたりの視線はぶつかっていた。