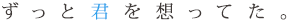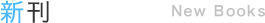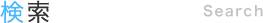夢に見る過去の恋人。それが誰なのか思い出せない――。
大学生の恵多には十代の頃の記憶が一部欠落している。
だが、現在恵多が恋をしているのは、一緒に暮らす叔父の章介だ。
章介の過保護さに辟易しながらも、気にしてくれることが嬉しくてたまらない。
実らない想いでも、この幸せが続くならそれでいい。
ところが、二人の間に性的な雰囲気が漂い始め、危ういバランスを保っていた関係が崩れていく。
思い悩んだ恵多は、再会した過去の恋人と付き合うが!?
過去の傑作『君といたい明日もいたい』が改題・大改稿のうえ新装版で登場!
オンライン書店
電子書店
登場人物紹介
-

- 恵多(けいた)
21歳の美大生。父子家庭だったが3年前に事故で父を失くしてから叔父と一緒に暮らしている。
-

- 章介(しょうすけ)
恵多の父が経営していた会社を継ぎ、保護者となった。その責任からか、異常に過保護な一面も。
試し読み
プロローグ
眼下に水面がある。
温かな湯がたっぷりと張られたバスタブ。そこに顎先まで身を沈めて、恵多は心地よさに溜め息をつく。すると、身体をやんわりと締めつけられた。
誰かが背後から腕を回して、抱いてくれているのだ。自分が背を凭せかけているのは、その人の身体だった。
腕の長さや、背に感じる硬い胸部や腹部からして、同性だろう。けれども違和感はなく、とても落ち着いて、それでいて身体が芯からドキドキする。
まるで夢のように心地よくて──これは夢なのだと、頭の端で知っている。
もう何度も何度も繰り返し見ている夢だ。目が覚めて、いつも落胆する。
現実の自分は、こんなふうに湯船に浸かることはできない。こんなふうに、誰かに身体を委ねることはできない。こんなふうに満たされた気持ちになることはない。
溜め息をつくと、湯に波紋が拡がる。
その波紋に重ねるように、耳元で男がなにかを言った。
自分は頷き、微笑む。
「──うん。約束だよ」
いつものように、そこで目が覚めた。
自分の部屋の木貼りの天井を、オレンジ色がかった眸で凝視して、恵多はついいましがた、夢のなかでした約束を思い出そうとする。
けれども、やはり思い出せなかった。
1
チューブの尻を人差し指と中指のあいだに挟む。そのまま首のほうまで、指に力を入れて扱く。小さな口からにょろりと出たペーストを歯ブラシでキャッチする。
恵多が緑色の柄の歯ブラシを咥えたところで、鏡のなかにぬうっと大きな男の姿がはいってきた。ただでさえ圧迫感のある身体が右腕を天井へと思いっきり突き上げて伸びをする。
「もはよ」
泡まみれの口でもごもごと言うと、
「あー」
顎にぽつぽつと生えた一晩分の髭を親指でさすりながら、男──仲里章介は低い声で洗面所の空気を震わせた。極太フレームの眼鏡に、縒れた鼠色のスウェットの上下。ぼさぼさの黒髪が眼鏡をなかば隠している。我が叔父ながらあまりのむさくるしさに、恵多は起き抜けからげんなりさせられる。
章介が黄色い柄の歯ブラシとぺったんこになったチューブを手に取る。
「もう、なひ」
恵多は口からブラシをいったん抜いて続ける。
「洗剤とかトイレットペーパーとかさぁ、いろいろなくなってきてんだよね。車出してよ」
「んなもん、近くのスーパーで学校帰りにでも買ってくればいいだろが」
章介は歯ブラシをコップに投げ戻すと、口内洗浄液がはいったボトルを?んだ。
「やぁだ。トイレットペーパーのロールなんて、持って歩きたくねーもん」
「なにいっちょまえにカッコ気にしてんだ」
「なら、カッコ気にしないショースケが買ってくればいいじゃん」
「俺は社長さんなの。忙しいの」
きついミントの刺激にしっかりしたラインの眉が軽く歪む。章介は最後に豪快な嗽をすると、青みのある液体を白いボウルにぶち撒けた……ボウルへと顔を伏せたまま、奥二重の目が上目遣いで、鏡越しにちらと視線を投げてくる。
目が合ったと思った瞬間、視線を外された。章介がぼそりと言う。
「土曜の午後、ホームセンターでいいな」
「ん」とそっけなく頷きながら、鏡のなかの自分の左頬に片えくぼが深く浮かぶのを恵多は見る。それを隠したくて、章介と入れ違いにボウルへと顔を伏せた。開いた口からとろつく白い液を垂らしていく。
水で口をすすいで身体を起こしたとたん、ロングスリーブTシャツの襟ぐりに男のしっかりした人差し指がかかった。
指先が素肌をカリッと?く。
「首んとこ伸ばして脱ぐ癖やめろって何度言えば……幼稚園児のお着替えか」
伸びて緩んだ襟から薄い肩がなかば露わになっていた。
「それと、そのショースケっていうベターッとした頭悪そうなアクセントやめろ。ショウスケ」
「……」
章介の手を弾く。
「そのむさい髭、とっとと剃れば?」
言い残して洗面所を出ると、反撃が声だけで追ってくる。
「二十一にもなって髭をめったに剃らなくていいガキは、楽でいいなぁ」
ひと回りと一歳も年下の甥おいを相手に、まったく大人げない。
とはいえ、いくぶんコンプレックスになっているところを突かれて、恵多は素直にムッとする。
天然木をふんだんに使ったリビングルームを横切って遮光カーテンを乱暴に開ける。
眩しい光。長いこと手を入れていない庭は枯れた雑草だらけだ。朝の冬空は青色セロファンみたいに、ぺらりとした質感だった。
左肩に手をやる。
そこにまだ留まっている、章介の指先の皮膚の温かさ、爪の硬さ。
小さなざわめきを掌でゴシゴシと擦り消し、大袈裟な瞬きで気持ちを切り換えた。